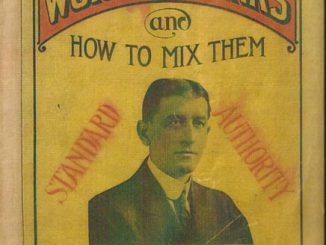日本に洋酒文化が定着していったプロセスを追う本シリーズ。その手がかりとして最初にスポットを当てたのが、大正期から現れたモダン・ガールたちだ。この時期の日本にカクテルというものが登場したと前回述べたが、今回はより多くのモダン・ガールたちに親しまれていたリキュールを紹介する。
ミント・リキュール1杯2500円也
そろそろモダン・ガールの項も終盤に近付いてきた。彼女たちは銀座を闊歩する戦前のトップレディーとして、たしかに虚像ではなく存在していた。
「ラヂオ」のアナウンサーやバス・ガール、丸ビルに勤めていた700人もの女性たちを筆頭とする彼女たちがどういう環境で何を考え、その後の戦争の時代にどう向かっていったかは「モダン・ガール論」(斎藤美奈子著)
に詳しいので、そちらをお勧めしたい。
戦前の銀座を颯爽と闊歩していたモダン・ガールたちは、その誰もがプース・カフェを口にしていたわけではない。何より作るのに手間がかかる上に、色分けに主眼をおいたカクテルだから飲み進むにしたがって甘さと味わいを度外視して加えられたさまざまな香りの混濁が口を襲うカクテルだからだ。
では、彼女たちがどんな洋酒を口にしていたのか。実はその答えは第一回から使わせていただいている藤原カムイ先生のイラストに忍ばせてある(今回に限り段落間のイラストそれぞれをクリックすると拡大するようにしているのでご覧いただきたい)。
この段の終わりの右のイラストに描かれた彼女の傍らに置かれた青緑色の酒……ジェットのミント・リキュールがその答えだ。昭和初期にトップクラスだったバー、たとえば「サロン春」で本物を頼むと一杯で60銭(ライスカレーがデパート食堂で20銭だから、これを仮に800円として、おおよそ一杯2500円位)も取られたことになる。だから、服や帽子、香水に出費のかさむ彼女たちが本物を口にできる機会は限られていたが、当時庶民が飲んでいたコピー物なら街角のスタンド・バーで10銭出せば飲むことができた。
彼女たちが三越や日劇で逢引き(デート)をする場合も、これならなんとかモダン・ボーイ君にも出せる金額で、「カフェーパウリスタ」の珈琲やエスキーモ(店がこう呼ぶことにこだわった)のアイスクリームで銀ブラを一休みしたあとで「ちょっと一杯飲んで行こうか」と言えることになる。
“素敵に気持ちがよい”ミント・リキュール

すでに昭和初期にはジェットの普及も全国に及んでいた。昭和7年のグルメガイドで洋酒80本の品揃えを誇る大阪戎橋北詰の「カフェー・ライオン」のマネジャーに売れ筋を尋ねた記者が「相変わらずウイスキーが六分、次はブラン(デー)、甘いものではペパーミント、キュラソー、ベルモットといった調子です」と聞いて、取材の終わりにはかなり酩酊しつつ別のカフェーに立ち寄り、その際に「二杯のペパーミントは白いマーブルの食卓に照映えて素敵に気持ちがよい」と書き残している。
ここまで読まれた読者のなかには、当時のモダン・ガールを偲んでミント・リキュールをストレートで飲んでみたいと思った方もおられるに違いない。残念ながら現在バーで一般に使われているミント・リキュールはキューゼニアにせよマリー・ブリザールにせよ、カクテルとして使われることを前提に作られているため、ストレートで飲むことを念頭に置いた造りにはなっていない。残念ながらストレートはお勧めできないのが実情だ。
ジェットもラベルで見て4世代以上前、昭和45年頃まで流通していたタイプの瓶(写真)をバーで見つけたら迷わず注文していただきたいが、よほどリキュールを揃えているバーでも現在は滅多に見かけない。
筆者は今から10年以上前に代々木上原のバーで口にする機会を得たのだが、いや、これは問答無用でうまかった。甘いことは甘いのだが、口で暴れる尖った甘さではない。柔らかく口内を包む優しい甘さにうっとりしているうちに、すがすがしくて優しいミントが口いっぱいに広がる。カクテルを敵視するフランスだが、ストレートで飲むリキュールは別なのも納得で、このジェットを口にすると肉やバターでこってりした口にさわやかな風が吹き抜ける。
大正のバーをしのぶ
さて、モダン・ガール原稿に最後まで付き合っていただいた読者の方にお礼代わりに打ち明けると、実は現在でも入手可能なストレートで飲んでいただきたいミント・リキュールが、2本存在する。
1つはデザートとしてリキュールを飲む文化が健在のフランスで100年以上前から作られているジファール社のマント・パスティーユ。香りはもちろん、入手しやすい価格(700ml/2500円前後)も魅力で、味はモダン・ガールの時代を偲ぶには十分だが、残念ながら透明な物しかない。
本稿を読んだ以上、味はもちろん、当時のモダン・ガールが「飲む宝石」として憧れていた色にどうしてもこだわりたい。そんなあきらめの悪い方にはマリエンホーフのグリーンミントという極めつけの逸品がある。こちらはドイツ産で6000円以上と、リキュールとしてはちょっと……いや、かなり勇気がいる値段だが、小さな業者が手作りで少量生産している。色は天然ミントから抽出した緑で無香料・無着色。味はバー向けに高級酒やレア物を扱う業務用酒販店バイヤーの折り紙つきなので試してみる価値はあると思う。
本稿の最後に、「鴻之巣」の奥田駒蔵とも親しかった詩人木下杢太郎の詩の一節をお贈りする。詩の中にもあるように、彼は「鴻之巣」でミント酒を好んで飲んでいたようで、別に「薄荷酒」という詩もあるのだが筆者の好みでこちらを掲示させていただいた。ミント酒を口に含みながら読んでいただきたい。
「五月の頌歌」木下杢太郎
さう云う五月が来るときは
河沿ひの酒場(バア)に入りて
われは静かに青きペパミントの酒を啜(スス)りて、
頌歌(ホメウタ)つくるを常とする。
小さな給仕(ボオイ)は給仕(ボオイ)とて
居睡(イネムリ)するのを常とする。
(画・藤原カムイ)
◆
《「洋酒文化の歴史的考察 I モダン・ガールは何を飲んでいたのか」は今回で終わりです。次週からは「洋酒文化の歴史的考察 II スパイ・ゾルゲが愛したカクテル」をお届けします》