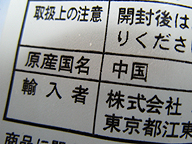《前回のつづき》今日のフランスのパティシエの全員がそう考えているのかどうかはわかりませんが、少なくとも伝統的にはそのようなルールなり、コモンセンスがあった/ある、のでしょう。
おそらくは、握る魚が生で切っただけのすしや、菓子に合わせるフルーツが非加熱であるというのは、フレンチの料理人やパティシエの目からすると技術者の介入がないか不足していると見えるのではないでしょうか。
では、日本料理はどのような考え方で行われているものと考えたらいいでしょう。日本でも、昔から混ぜる、煮る、焼くは普通にやってきました。明文化されないまでもその技術は伝承されてきています。ただ、とくにコールドチェーンが発達したこの数十年は、切るとか「包丁する」ということに集中して、技術や考え方が発達してきたように思われます。
先日、NHK「プロフェッショナル――仕事の流儀」で日本料理の山本征治氏が登場した回を面白く見ました。
氏の説明の中で、イカの身の厚みの中心に甘味があるので、それを舌に感じやすくするために身の中心より下まで包丁で切り込みを入れるという話がありました。何かを混ぜたり加熱調理するのではなく、包丁によって本質を引き出そうとするアプローチだと言えるでしょう。
また、アユを焼く際、アユの口を開いてやって頭を乾かすことで食感を高め、内臓を突いて体液を流すことで臭みを香りとしてまとわせるということも説明されていました。
フレンチ的なアプローチでいけば、イカに何を使って甘味を付けるか、アユの臭みを何で抑え、何で香りを付けるかと考えるかも知れません。それを、氏の場合はその単一の素材そのものが秘めているもので実現しようとしているように受け取りました。
山本氏の場合、生で切っただけのものが料理ではないと考えることはありません。録画していないのでお話を正確に再現できませんが、「たとえば生のキュウリを半分に切って出すとする。それは、『半分に切って持ちやすくして、手に持って食べたほうがおいしいと思ったのでそうしたんですよ、あなた(のため)に』ということが、料理でしょう」と説明されていました。錬金術とは全く異なる仕事のあり方を、ズバリと説明してもらったように感じました。
こうした考え方が育まれる背景にあるのは、化学に対しての物理学とも言えるかもしれませんが、より重要なのは日本人の霊性のように思われます。
ここで言う霊性というのは別にオカルトめいたことではなくて、鈴木大拙が使った言葉で、いわば日本人の宗教感覚やそれによって培われた文化的側面です。根底には日本人の自然との共生感覚があり、禅などある種の仏教によって特質が際立たせられ、たとえば武士道や茶道や華道などさまざまな“○○道”に引き継がれているというものです。それらの中では、技術と表裏一体の形で“もてなし”という人間関係が表現されます。
いいえ。話が宗教的なほうへ向かってしまうので、このあたりでやめておきましょう。西洋料理と今日の日本料理とで、出発点がかなり違うということに改めて気付かされて驚いたり、面白く感じたりしているとだけご理解ください。
そして、いずれにせよ、私はこの東西両方の考え方と方法に前向きな興味を持っています。その興味から、昨年閉店してしまったフェラン・アドリア氏の「エル・ブリ」※(スペイン)にも関心を持っていました(おそらく、私には身分違いで、店が継続していても客として訪店することはなかったでしょう)。《つづく》
※店名「El Bulli」は、スペイン語(カスティジャーノ)の順当な読み方では「エル・ブジ」となるようですが、山本益博氏は「エル・ブリ 想像もつかない味」(光文社)の冒頭で、店のあるカタルーニャでの発音は「エル・ブリ」であり、経営者にも聞いて確認したそうであると説明しています。
※このコラムはメールマガジンで公開したものです。