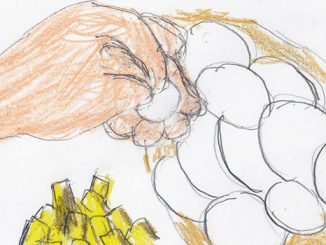沖田修一監督による自主製作映画「おーい! どんちゃん」をご紹介する。作品毎に印象的な食べ物を登場させる沖田監督だけに、本作も要所要所に食べ物のシーンを絡めている。
沖田修一監督の作品は、当コラムでも「南極料理人」(2009,本連載第38回参照)、「モリのいる場所」(2018、本連載第186回参照)を紹介している。本作は2013年、娘(どんちゃん)が生まれたことをきっかけに沖田監督が購入したハンディカムを使い、ワークショップで出会った俳優たちと一緒に、何か短いドラマのようなものを作ろうと、遊ぶように始まった。生後半年だったどんちゃんの成長と共に撮影規模も大きくなっていき、どんちゃんが話せるようになった3年後に撮影は終了した。
プライベートフィルムの側面があるため、これまで上映機会は映画祭や特集上映などに限られていたが、さる2月21日に2週間限定で劇場公開が実現した。DVD化や配信はされないと思われるので、観る機会が見つかれば迷わず映画館に駆けつけて欲しい。
※注意!! 以下はネタバレを含んでいます。
トマトバンバンジーと子だくさん男

道夫(坂口辰平)、えのけん(大塚ヒロタ)、ぐんじ(遠藤隆太)の3人は、売れない俳優。ある日、3人が暮らすシェアハウスの前に、女の赤ちゃんが置かれていた。赤ちゃんは「どんちゃん」と名付けられ、3人は慣れない育児に奮闘する。やがて、季節は巡り、年は過ぎ、転機が訪れる、というシンプルなストーリーである。
3人の男による育児ストーリーは、ジョン・フォード監督の「3人の名付親」(1948)や、同作を下敷きとした「赤ちゃんに乾杯!」(コリーヌ・セロー監督、1985)と、ハリウッドリメイクの「スリーメン&ベビー」(レナード・ニモイ監督、1987)を想起させる。また、子供の成長に合わせて撮影が進行する作品としては、リチャード・リンクレイター監督の「6才のボクが、大人になるまで。」(2014)に通じるものがある。
序盤のヤマ場である赤ちゃんを見つけるくだり。3人は2階のベランダで、トマトをのせたバンバンジーをワインのつまみにしながら、人生ゲームを楽しんでいる。
カメラの性能が上がり、俳優の肌荒れも映ってしまう昨今、トマトは美容に効果があるから毎日食べるべきだと、調理担当であるぐんじはトマト嫌いの道夫に向けて言う。道夫は頑張って食べようとするが戻してしまい、皆にからかわれる。
一方、えのけんの人生ゲームは絶好調。立て続けに子供が生まれる。昭和エンタメに詳しい道夫は、「おまえはディック・ミネか」と突っこむ。ディック・ミネと言えば、映画ファンとしては「鴛鴦歌合戦」(マキノ正博監督、1939)の殿様役が記憶に残る、子だくさんで有名な歌手である。えのけんが他の2人からおもちゃのドル札を祝儀としてせしめる中、階下からの赤ちゃんの鳴き声が次第に大きくなっていく。下に降りてみると、玄関先にベビーカーに乗った赤ちゃんと、えのけん宛ての元カノの置手紙が。すべてを察した道夫とぐんじが、えのけんに祝儀の追い銭を渡すというオチになっている。
周回遅れのカレーと決意のゴーヤーチャンプルー
育児経験のない3人が、大慌てでどんちゃんのおむつを替えたり、ミルクを飲ませたりする様子を観ながら筆者が想像したのは、この先3人がどんちゃんと楽しい時間を過ごした末に、どんちゃんの母親の登場、からの、3人とどんちゃんとの別れという、「クレーマー、クレーマー」(ロバート・ベントン監督、1979、本連載第75回参照)のような運命が待っているのではないか、という展開。これを思うのはおそらく筆者だけではないだろう。しかし本作では、そんな安易な想像をいい意味で裏切ってくれる。
どんちゃん登場から3年後のドラマ後半、道夫は家をのぞく不審な女の姿を見かけるが、その後、すし職人役のオーディションでインド人映画監督(Vasu seshadri)に気に入られ、マサラ映画の撮影でボリウッドに行くことに。
2カ月後、道夫が頭にターバンを巻いた姿で帰国すると、道夫が留守の間に、えのけん、ぐんじ、どんちゃんが、あの不審な女と共に暮らしていることが明らかになる。女はどんちゃんの母親である吉野川佳織(どんちゃんママ)であった。
道夫の理解がまったく追いつかない中、インド帰りの道夫にカレーを振舞う佳織。道夫は佳織に、子供を置いていなくなっておいてと怒りを爆発させるが、他の者たちにとってそうゆう修羅場はもう終わった話。完全に置いてきぼりを食らった道夫にどんちゃんがかける、本作唯一のセリフが洒落ているのだが、そこは作品を観ていただきたい。
そして舞台は再び2階のベランダに。どんちゃんが佳織と幼稚園に向かった後、再び人生ゲームに興じる3人。今回の料理はゴーヤーチャンプルーだ。ゴーヤはお肌にいいからと道夫にすすめるぐんじ。えのけんは相変わらず人生ゲームで子宝に恵まれる。するとまた赤ちゃんの声が。今度は空耳だった。そんな中、大事な話を切り出す道夫とぐんじ。この先のやり取りがなかなか感動的なのだが、またもや肩透かしで笑いをとるのが沖田監督らしいところである。
映画好きならではの場面たち
本作には沖田監督自身も、ぐんじの所属する劇団の主宰で、精神疾患により地方の病院に入院中の富田役で出演している。映画の中盤でぐんじが富田を訪ねるくだりがあるのだが、まるで病院から逃げてきたかのようにお仕着せの患者衣のままの姿で富田が登場。食堂に入ると食欲旺盛に丼をかっ食らい、ぐんじの食べているそばにも手を出す始末。その有様は「幸福の黄色いハンカチ」(山田洋次監督、1977、本連載第69回参照)の出所直後の島勇作(高倉健)のようだ。
また、3人の友人で坂本(師岡広明)との結婚を控えたあかり(宮部純子)が、ウエディングドレスを着るためのダイエットでランニングするシーンは、「ロッキー2」(シルヴェスター・スタローン監督、1979)のランニングシーンの完コピとなっている。
その他、えのけんというニックネームは「エノケンのちゃっきり金太」(山本嘉次郎監督、1937)や「虎の尾を踏む男たち」(黒澤明監督、1945)に出演した昭和の喜劇王、榎本健一にちなんだものと思われる。道夫が加東大介主演の「南の島に雪が降る」(久松静児監督、1961)を観に行くと言ったり、DVDでポール・トーマス・アンダーソン監督の「ザ・マスター」(2012)を観ながら、同作で主演を務めたホアキン・フェニックスと今は亡きリバー・フェニックスの兄弟関係に言及するなど、名優へのリスペクトも頻繁に出てくる。
本作の撮影開始当初は少人数編成だったため、撮影や録音にはスタッフ・キャスト問わず手すきの人が動員された。その名残りはスタッフクレジットに見ることができる。一方で色合わせを名カメラマンの芦沢明子が務めるなど、要所はしっかりと押さえている。
- 南極料理人
- Amazonサイトへ→
- 本連載第38回
- https://www.foodwatch.jp/screenfoods0038
- モリのいる場所
- Amazonサイトへ→
- 本連載第186回
- https://www.foodwatch.jp/screenfoods0186
- 6才のボクが、大人になるまで。
- Amazonサイトへ→
- 三人の名付親
- Amazonサイトへ→
- 赤ちゃんに乾杯!
- Amazonサイトへ→
- スリーメン&ベビー
- Amazonサイトへ→
- 鴛鴦歌合戦
- Amazonサイトへ→
- 幸福の黄色いハンカチ
- Amazonサイトへ→
- 本連載第69回
- https://www.foodwatch.jp/screenfoods0069
- ロッキー2
- Amazonサイトへ→
- エノケンのちゃっきり金太
- Amazonサイトへ→
- 虎の尾を踏む男たち
- Amazonサイトへ→
- 南の島に雪が降る
- Amazonサイトへ→
- ザ・マスター
- Amazonサイトへ→
【おーい!どんちゃん】
- 公式サイト
- https://oooooi.wixsite.com/homepage
- 作品基本データ
- 製作国:日本
- 製作年:2022年
- 公開年月日:2025年2月21日
- 上映時間:157分
- 配給:沖田修一
- カラー/サイズ:カラー/16:9
- スタッフ
- 監督・脚本:沖田修一
- 撮影:道川昭如、三村和弘、御木茂則、沖田修一、手のあいた人
- 録音:落合諒磨、山本タカアキ、高田伸也、清水裕紀子、中野雄一、手のあいた人
- 音楽:澤口希
- 色合わせ:芦沢明子、廣瀬亮一
- キャスト
- 吉野川きみこ(どんちゃん):どんちゃん
- 長谷道夫(道夫):坂口辰平
- 榎本健(えのけん):大塚ヒロタ
- 郡司洋一郎(ぐんじ):遠藤隆太
- 坂本:師岡広明
- あかり:宮部純子
- 吉野川佳織:どんちゃんママ
- 富田:沖田修一
- 事務所社長:宇野祥平
- 公園の父親:山中崇
- キャンプ場の男:黒田大輔
- インド人映画監督:Vasu seshadri
(参考文献:KINENOTE)