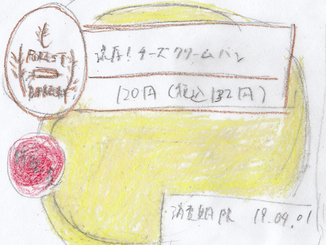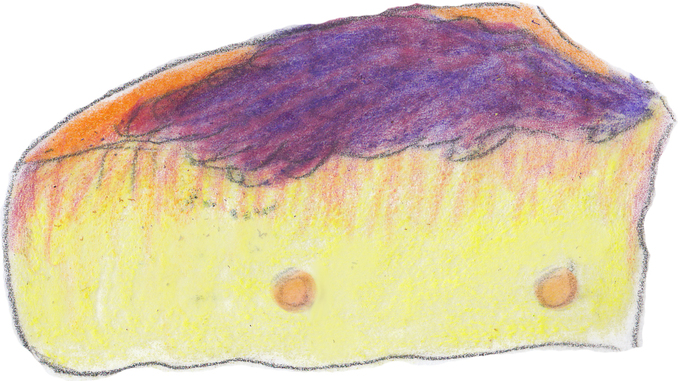
今回紹介する「フロマージュ・ジャポネ」は、2022年公開のNORIZO監督作品「Vin Japonais ヴァン・ジャポネ the story of NIHON WINE」の姉妹編にあたる、日本のチーズについてのドキュメンタリーである。前作同様、クラウドファンディングで集めた資金をもとに製作されている。
現在、日本には340以上のチーズ工房がある。本作は5社のチーズメーカーと、北海道から本州、九州まで、18のナチュラルチーズの工房に取材し、担当者へのインタビューとチーズの製作現場、商品などのカットを織り交ぜながら構成している。
- 「Vin Japonais ヴァン・ジャポネ the story of NIHON WINE」
- Amazon Prime Video
- 本連載第295回
- https://www.foodwatch.jp/screenfoods0295
※注意!! 以下はネタバレを含んでいます。
プロセスチーズからナチュラルチーズへ
1960年代、パン食など日本の食卓の洋風化が進み、1963年にチーズが学校給食に導入されたことも相まって、チーズの消費量が増加した。このチーズの普及に大きな役割を果たしたのが、チーズメーカーが製造したプロセスチーズである。
プロセスチーズは、ナチュラルチーズを粉砕し、乳化剤を加え、加熱して溶かしたものを型に入れて作られ、ブロックチーズ、6Pチーズ、ベビーチーズ、スライスチーズ、シュレッドチーズ、粉チーズなどさまざまな形で私たちの食生活に浸透している。メーカーの研究開発により、とろけるチーズやこんがり焼けるチーズなど、ナチュラルチーズが持つものに似た特性を持つものも現れている。
その一方、1980年代のピザブーム、チーズケーキブーム、1990年代のワインブームなどが起こるなかで“本物のチーズ”へのニーズが高まり、酪農経営の新しい道として選ぶ人たちも現れ、国内でも消費者向けのナチュラルチーズ製造が活発になった。年々チーズ工房の数は増え、品質や人気で欧米のものにも負けない“日本のチーズ”が生まれつつある。
“テロワール”を生かしたチーズ作り
生乳の生産量が日本一の“酪農王国”北海道には、数多くのナチュラルチーズの工房がある。
コンテチーズの製法を取り入れたハードタイプのチーズ「フロマージュド 美瑛 夏ミルク」で、2022年にJAPAN CHEESE AWARDS 2022(チーズプロフェッショナル協会)グランプリを受賞した美瑛放牧酪農場では、美瑛の丘陵地形を生かした半地下の熟成庫に、美瑛産のトドマツや美瑛軟石を使い、美瑛でしかできないチーズを作っている。
道内一の酪農地・十勝では、ラクレットチーズを作るために管内10カ所のチーズ工房が十勝品質事業協同組合(TOKACHI PRIDE)を結成し、共同で熟成庫を運営。アルカリ質の温泉水で磨き上げることでオレンジ色に染まり、コクはありながらクセの少ないまろやかな味のチーズに仕上げている。
ワインの産地特性を示す“テロワール”(terroir/土地、産地、土壌)という用語があるが、本作に登場する各地のチーズ工房での事例は、チーズにもテロワールがあることを示している。
チーズとワインの“マリアージュ”

北海道虻田郡喜茂別町にあるチーズ工房タカラでは、
長野県東御市で1982年に創業したアトリエ・ド・フロマージュでは、隣接する小諸市にあるマンズワイン小諸ワイナリーのワインでウォッシュしたチーズを作っている。WORLD CHEESE AWARDS(英Guild of Fine Food社)2021でSUPER GOLD(BEST16)に選ばれたブルーチーズ「翡翠」は、小諸ワイナリーのワインと相性がよいという。
放牧したヤギのミルクを原料とした熟成チーズを作っている広島県三次市の三良坂フロマージュでは、同市にのワイナリーVinoble Vineyardと手を取り合って、三次のテロワールを世界に発信していこうとしている。
土に生えた草を食べて育った動物の乳から作ったチーズと、土で育ったブドウからできたワイン。テロワールが同じチーズとワインの“マリアージュ”が全国各地に存在することを本作は教えてくれる。
低温殺菌した生乳を使い、「誰でも食べられる穏やかな」ナチュラルチーズ作りを心がけている島根県雲南市の木次乳業の川本さんと、関連会社のワイナリー奥出雲葡萄園で「素直で優しいワインを目指している」安部さんが握手するシーンは、チーズとワインの“マリアージュ”の象徴のように映る。
“ホエイロス”対策の取り組み、その他
ところで、チーズを作る工程では、生乳はチーズになるカード(凝乳)とホエイ(乳清)に分離される。カードが1割程度なのに対してホエイは9割程度となるのだが、そのほとんどが廃棄されているのが実情だ。しかし、ホエイは栄養価が高く、これを活用しようとする各地のチーズ工房の取り組みも、本作は紹介している。
佐賀県嬉野市のナカシマファームは、ホエイを煮詰めてカラメル状にしたブラウンチーズの製品化に日本で初めて成功。JAPAN CHEESE AWARD 2018で金賞・部門最優秀賞、WORLD CHEESEAWARDS 2019でBRONZEを受賞するなど高い評価を得ている。
生乳の生産量が本州一の栃木県那須塩原市にあるフィンランドの森チーズ工房メッツァネイトでも、ホエイを原料としたブラウンチーズを作っている。東京のど真ん中、渋谷にあるチーズ工房CHEESE STANDでは、ブラウンチーズの他、ホエイジャムも作っている。
その他、日本のナチュラルチーズ界のパイオニアの一つと言える北海道上川郡新得町共働学舎新得農場の宮嶋望氏、新鮮な水牛のミルクで作るモッツァレラチーズにこだわる千葉県木更津市クルックフィールズの竹島英俊氏、千葉県夷隅郡大多喜町の古民家で“オール千葉”のチーズを作っているチーズ工房【千】senの柴田千代氏など、単独でも一本のドキュメンタリーが作れそうな個性的な生産者が多数出演している(実際に竹島氏はテレビ朝日「食彩の王国」、柴田氏はTBS「情熱大陸」で取り上げられたことがある)。
性別・世代を超えた将来に期待
日本産チーズのこれからの課題としては、国内消費の拡大と生産の拡大が挙げられる。日本のチーズ消費量は欧米に比べるとおよそ10分の1にとどまっている。逆に言えば、まだ食べてもらえる、成長の余地があるということだ。また、国産ナチュラルチーズの生産量は年々増加しているものの、国内のナチュラルチーズ消費量の約85%は輸入品というのが現状である。本作ではこうした課題に需要者側で取り組んでいる活動も紹介している。
気になったのが、需要者側を代表する制作実行委員会の5人が全員女性だということ。老若男女関係なく、日本チーズの将来に真剣に向き合うようになったそのときこそ、日本チーズの発展があるように感じた。
【フロマージュ・ジャポネ】
- 公式サイト
- https://nihoncheese.jp/
- 作品基本データ
- 製作国:日本
- 製作年:2024年
- 公開年月日:2024年4月12日
- 上映時間:106分
- 製作会社:CruX
- 配給:フロマージュ・ジャポネ 制作実行委員会
- カラー/サイズ:カラー/シネマ・スコープ(1:2.35)
- スタッフ
- 監督・製作:NORIZO
- 制作実行委員会:佐藤優子、山田好美、佐藤玲子、丹下慶子、磯部美由紀
- キャスト
- 伊藤博昭(雪印メグミルク株式会社阿見工場製造課)
- 太田丈尋(雪印メグミルク株式会社商品開発部)
- 水野礼(森永乳業株式会社チーズ研究室長)
- 関根彩菜(エムケーチーズ株式会社品質管理室)
- 渡邉武志(株式会社明治発酵開発研究部)
- 佐藤雅幸(タカナシ乳業株式会社商品本部本部長)
- 小熊章子(美瑛放牧酪農場)
- 宮嶋望(共働学舎新得農場)
- 長原ちさと(TOYO Cheese Factory)
- 斉藤愛三(チーズ工房タカラ)
- 近藤裕志(ニセコチーズ工房)
- 本間幸雄(しあわせチーズ工房)
- 塩川和史(アトリエ・ド・フロマージュ)
- 髙橋雄幸(デーリィーファーム富士山)
- 山川将弘(チーズ工房那須の森)
- 人見厚子(フィンランドの森チーズ工房メッツァネイト)
- 天谷聡(あまたにチーズ工房)
- 藤川真至(CHEESE STAND)
- 竹島英俊(クルックフィールズ)
- 柴田千代(チーズ工房 【千】sen)
- 川本英二(木次乳業)
- 松原正典(三良坂フロマージュ)
- 中島大貴(ナカシマファーム)
- 里村貴司(さとむら牧場)
- 久田早苗(「チーズ王国」創業者)
- 本間るみ子(チーズ輸入会社「フェルミエ」創業者)
- 佐藤優子(チーズプロフェッショナル協会顧問)
- 山田好美(レコール・デュ・ヴァン主任講師)
- 佐藤玲子(レザンドール ワインサロン主宰)
- 丹下慶子(パンと料理の教室「さくらキッチン」主宰)
(参考文献:KINENOTE)