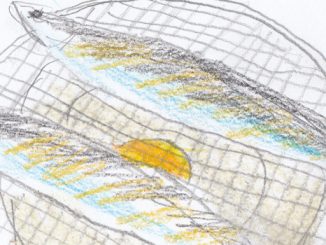現在公開中の「みをつくし料理帖」は、髙田郁による同名の時代小説シリーズ(ハルキ文庫)が原作。19世紀前半、文化年間の江戸を舞台に、女性の料理人・澪の奮闘を描いたもので、2012年と2014年にテレビ朝日にて北川景子主演でテレビドラマ化、2017年にNHKにて黒木華主演で再ドラマ化されている。今回の劇場用映画は「角川春樹最後の監督作」として製作された。
食は人の天なり
「みをつくし料理帖」のタイトルが示す通り、本作のもう一つの主役は料理である。10巻以上に及ぶ原作を2時間弱の尺に収めるためにエピソードはだいぶ省略されているが、主眼は上方と江戸の食文化の違い。大坂(今の大阪)出身の澪(松本穂香)が、料理人は男と決まっていた時代に女性であることのハンデに加え、食文化の違いを乗り越えて、江戸と上方の“いいとこどり”の味で神田の「蕎麦処 つる家」を繁盛店にしていく過程が描かれている。
澪の料理の改善のヒントとなったのは、身分を隠して「つる家」を訪れる御膳奉行(将軍に供する食事を管掌する職)の小松原(窪塚洋介)と町医者の源斉(小関裕太)の言葉。口から摂るものだけが人の体を作るという意味の「食は人の天なり」(※1)を胸に、澪は料理の腕を上げていく。
また、吉原の遊郭「翁屋」の伝説の花魁「あさひ太夫」(奈緒)が、10年前の享和2年(1802)に大坂の町を襲った大洪水で生き別れになった親友・野江であることを知った澪が、たやすく会うことがかなわない親友と懐かしい上方の味の料理を通じて親交を取り戻していく過程を、角川監督はこれまでのスペクタクル重視の演出を封印し、丹念に描いている。
本作に登場する料理は原作の各巻末に収録されている「澪の料理帖」をもとに「ラストレシピ〜麒麟の舌の記憶〜」(本連載第163回参照)でも料理監修を務めた服部幸應が率いる服部栄養専門学校のチームが忠実に再現している。
では、ストーリーとリンクした料理の数々を順にみていこう。
※料理や関連場面は公式サイトで「澪の料理帖」 「メイキング映像」も公開されていますが、劇場での初見を楽しみにされる方は以下は観覧後にお読みください。
澪の料理帖
①牡蠣の味噌仕立て
澪が「つる家」で初めて作らせてもらった料理。上方の調理法だが、牡蠣は七輪で焼いて食べるのが当たり前の江戸っ子には理解されず「せっかくの深川牡蠣を」「ぼんやりした味」と、ろくに箸も付けずに帰ってしまう。小松原は「うまい」ではなく「面白い」という感想を述べる。
②ひんやり心太(ところてん)
八朔(8月1日)の吉原のお祭りの日、「つる家」の店主・種市(石坂浩二)と源斉と共に吉原を訪れた澪は露店で心太を食べるが、黒蜜をかける上方とは異なり、酢醤油をかけて一本箸で食べるスタイルに衝撃を受け、この心太をヒントに作った心太。江戸では乾燥寒天(天草から煮出して作った寒天を凍結乾燥したもの)を使うのが一般的だったところ、澪は上方式にさらし天草(海藻の天草をそのまま天日乾燥させたもの)から寒天を作り、江戸式に酢醤油で食べる「ひんやり心太」とし、これを「つる家」で出したところ好評を博する。上方と江戸の味を融合させた料理の第一号。
③とろとろ茶椀蒸し
種市から「つる屋」を引き受けることを決心した澪は、大坂での奉公先「天満一兆庵」の元女将(ご寮さん)で一緒に江戸に出てきた芳(若村麻由美)がかんざしを売った金でいちばん上等な鰹節を入手する。澪は、その鰹節からとった江戸前のだしと上方の昆布だしを合わせ、すべての料理の基本となるだしを完成させる。そのだしで最初に作ったのが「天満一兆庵」でも人気があった「とろとろ茶碗蒸し」だった。
これは、上方で始まったとされる茶碗蒸しがまだ知られていなかった江戸でたちまち評判となり、江戸時代の「ミシュランガイド」ともいうべき「料理番付」でいきなり関脇を取る。この料理番付は実在したもので、江戸っ子の食への関心の高さがうかがえる。
「とろとろ茶碗蒸し」の評判はあさひ太夫も知るところとなり、上方の味を懐かしむ太夫は「翁屋」の料理番・又次(中村獅童)に頼んで「つる家」から取り寄せようとするが、器が足りず一輪挿しの竹を使うことに。これがヒントになり「とろとろ茶碗蒸し」のテイクアウトも始まる。
④あさひ太夫のお弁当

「料理番付」で最高位の大関(※2)「日本橋登龍楼」の店主・采女宗馬(「料理の鉄人」の鹿賀丈史)は「つる家」の成功を妬み、「とろとろ茶椀蒸し」の味を盗んだうえ、「つる家」を放火する挙に出る。
すべてを失った澪の住む長屋を又次が訪ねてきて、あさひ太夫のために故郷の上方をしのぶ料理を作ってくれと頼む。又次が差し出した弁当箱には、小判に添えて手紙が。あさひ太夫が野江であることを知った澪は、感謝を込めておぼろ昆布(昆布の表面を薄く削ったもの)を巻いた俵型の握り飯と砂糖を使わない「巻き焼き」の玉子焼きをこしらえる。
⑤牡蠣の宝船
新装開店なった「料理処つる家」で最初に出した料理。船形にした昆布に牡蠣を並べて酒蒸し焼きにしたもの。澪はこれで不評だった「牡蠣の味噌仕立て」のリベンジを果たす。
⑥金柑の蜜煮
他の遊女と客とのトラブルに巻き込まれて負傷したあさひ太夫のために、又次が澪に依頼した料理。かつて野江が具合の悪い時にこれを食べていたことを覚えていた澪はあさひ太夫の体調を案じる。
⑦こぼれ梅
「つる家」の常連客で戯作者の清右衛門(モデルは曲亭馬琴、演:藤井隆)の妻・お百(薬師丸ひろ子)に紹介された味醂からとった搾り粕をほぐしたもの。満開の梅がこぼれたように見えるため「こぼれ梅」と呼ばれ、その甘さは大坂の女性や子供のおやつにも好まれていた。借りたお金と感謝の手紙を添えて、幼い日に口にした思い出の味をあさひ太夫に食べさせようと、澪が「翁屋」に持参する。
⑧鼈甲珠
晴右衛門があさひ太夫のことを戯作にしようとしていることを知った澪は、あさひ太夫を守るために晴右衛門と賭けをする。もし自分の作った料理が驚くほどおいしかったら一つ願いを聞いてもらう。そのために作ったのが玉子の黄身の味噌漬け「鼈甲珠」。砂糖の代わりにこぼれ梅を使い、ふくいくとした香りと鼈甲色の輝きで食欲を刺激する。玉子の滋養で疲れ目への効果もある。
角川映画の歴史を辿るキャスティング
本作は、「角川春樹最後の監督作」ということで、歴代の角川映画のキャストが大挙出演し、角川映画の歴史を辿るものとなっている。
角川映画第一作「犬神家の一族」(1976)で金田一耕助を演じた石坂浩二(種市役)をはじめ、“角川三人娘”からは「野生の証明」(1978)でデビューした薬師丸ひろ子(お百役)と「伊賀忍法帖」(1982)でデビューの渡辺典子(つる家の客・お満役)、その他「野獣死すべし」(1980)の鹿賀丈史(采女宗馬役)、「スローなブギにしてくれ」(1981)の浅野温子(澪の住む長屋の隣人・おりょう役)、「湯殿山麓呪い村」(1984)の永島敏行(翁屋の楼主・伝右衛門役)、「メイン・テーマ」(1984)の野村宏伸(つる家の常連客・清八役)、「天と地と」(1990)の榎木孝明(小松原の上司・駒沢弥三郎役)らが出演。
また角川書店退社後に角川春樹が手がけた作品からは「男たちの大和/YAMATO」(2005)の反町隆史(易者・水原東西役)、中村獅童(又次役)、松山ケンイチ(吉原の無頼漢役)、「蒼き狼 〜地果て海尽きるまで〜」(2007)の若村麻由美(芳役)らが顔を見せている。
※1 『徒然草』第122段に「次に食は人の天なり。よく味をとゝのへ知れる人大なる德とすべし」とある。
※2 他に「八百善」などの破格の名店は番付中央に別格扱いで掲載されていた。
【みをつくし料理帖】
- 公式サイト
- https://miotsukushi-movie.jp/
- 作品基本データ
- 製作国:日本
- 製作年:2020年
- 公開年月日:2020年10月16日
- 上映時間:131分
- 製作会社:映画「みをつくし料理帖」製作委員会(企画:角川春樹事務所/制作:楽映舎)
- 配給:東映
- カラー/サイズ:カラー/シネマ・スコープ(1:2.35)
- スタッフ
- 監督:角川春樹
- 脚本:江良至、松井香奈、角川春樹
- 原作:高田郁
- 制作統括:遠藤茂行
- プロデューサー:前田茂司
- 撮影:北信康
- 照明:渡部嘉
- 美術:清水剛
- 音楽:松任谷正隆
- 主題歌:手嶌葵
- 料理監修:服部幸應
- キャスト
- 澪:松本穂香
- 野江(あさひ太夫):奈緒
- 又次:中村獅童
- 芳(ご寮さん):若村麻由美
- おりょう:浅野温子
- 清右衛門:藤井隆
- 水原東西:反町隆史
- 小松原(小野寺数馬):窪塚洋介
- 永田源斉:小関裕太
- 清八:野村宏伸
- 菊乃:衛藤美彩
- お満:渡辺典子
- 卯吉:村上淳
- 伝右衛門:永島敏行
- 吉原の無頼漢:松山ケンイチ
- 駒沢弥三郎:榎木孝明
- 采女宗馬:鹿賀丈史
- お百:薬師丸ひろ子
- 種市:石坂浩二
(参考文献:KINENOTE)