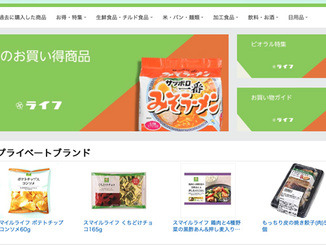日本経済新聞の土曜朝刊に別刷で付く「日経 PLUS1」の1月10日の号、「楽食探訪」という欄に宮崎県の千切り大根(東日本で言う切干大根を、西日本では千切り大根と呼ぶ。以下千切り大根)の記事を書かせていただいた。まだ古紙回収に回っていなかったら、ぜひご覧いただきたい。そのこぼれ話から。
取材に向かったのは、国内最大の産地である宮崎県国富町。JA宮崎中央千切り出荷場の方に話をうかがった。千切り大根は、生のダイコンを細かく刻み(同JAの場合は、2.5mm×5.5mm×100~150mmのサイズ)、これを圃場に設置したネットに広げて、日光と乾燥した寒風にさらして乾燥させる。
国富町では夏の終わりにダイコンを植えるが、それがちょうど太り出した頃に内陸から冷たく乾いた風が吹き下ろすようになる。栽培と風のタイミングが絶妙で、その風を生かしやすい平地があり、しかも気温が氷点下になりにくく、ダイコンを凍らせる失敗が少ない。このため、かつては愛知県が主産地だったが、この一帯が一躍大産地として頭角を現した。
とは言え、ご多分に漏れず、近年は千切り大根の主産地も中国にシフトしてきた。国産の生産量は年間2000~2500tで、その9割を宮崎県が賄う。それに対して中国産は2005年度で6000t以上が輸入されている。圧倒的だった。
ところが、06年以降は年々減少傾向を見せ、さらに例のギョーザ事件で一気に輸入量が減った。手元に正確な数字はないが、8月までの実績で2500t程度なので、恐らく05年から半減というところだろう。日本側が買わなくなったのか、中国が出さなくなったのかは分からない。とにかく減った。
頭を抱えたのは、流通と惣菜などを含む食品・外食企業だ。千切り大根は青果に比べて価格や量が年間を通じて安定しているから、いつでも野菜料理が作れるということで、惣菜、給食、居酒屋などでは多用するようになっていたからだ。勢い、国内産地に「もっと出して」という電話が殺到する。もちろん、同JAにも連日のように催促や価格の打診がある。
千切り大根は約1年分を冷凍倉庫に保管している。それをどんどん出せば現金が入るわけだが、もしそれで倉庫が空になれば、「欠品」としてどんな仕置きが待っているかわからない。同JAは、08年は先を読みながら、客先の事情を判断しながら、頭を下げ下げ、出荷量の調整に苦心した。さらに、今期の生産は夏の終わりの雨で作付けが遅れ、なかなか新ものが倉庫に入って来ず、暮れはひやひやし通しだったという。
この采配を振るっていた同JAの長嶺靖さんという人は、もともと食品会社に勤めていた人で、流通、食品、外食の事情や考え方に詳しい。とにかく欠品だけは避けるという判断を下すのも、長嶺さんは速かった。
長嶺さんが千切り大根を担当するようになったのは、約3年前のこと。着任してすぐに、千切り大根生産者にリクエストしたことがあった。出荷の際にビニール袋で梱包してくれということだ。
ネットの上で乾燥した千切り大根は、端からじゅうたんを巻くようにしてロール状にして運び出す。これを、以前は裸のまま軽トラックの荷台に積んでいた。長嶺さんは、それを見てすぐにNGを出した。汚れるし、農家の軽トラックは機械や資材などいろいろなものを積むもの。異物混入の危険があると見たわけだ。
長嶺さんにとっては食品を扱う仕事として当然のことだったが、生産者にしてみれば大きなものを袋に入れるので、今まで1人でもできた積み込み作業が2人単位となる。「長年なんともなかったのに、なぜ今変えるのか」と、最初不評だった。それをなだめながらすかしながらやって来たところ、最近は「このほうがきれいでいいね」と、生産者の意識が変わってきた。
袋には、生産者の番号と収穫日をペンで記入する。こうした簡単なことからトレーサビリティの確立を進め、今はコンピュータで管理するようになっている。一方で、特別栽培のものをほかの製品と分けて集出荷するようにした。ニーズがあると分かっていたからだ。そして、その分の価値を引き上げ、高級スーパーなどを中心に引き合いを増やしている。それに合わせて、特別栽培に取り組む生産者を増やしている。
ただし、栽培そのものについてはあまり詳しくないという自覚があり、無理強いはしない。生産者の事情と意向を聞き、JAの栽培指導員とも連携して、一本釣り式に誘いながらじわじわと進めている。
また、生産者や出荷場のスタッフをスーパーなど小売りの現場でのデモに誘い、売場を目で見、肌で感じ、消費者と言葉を交わす機会を増やしている。一度行くと、楽しさ、プライド、喜ばれたいという意識が増し、誰しも仕事に対する姿勢が変わるという。
以上を読んで、とくに変わった話ではないと感じる人も多いだろう。しかし、今の国内農業にとって最も必要なのは、この長嶺さんのような役割を演じる人なのだと、強く感じている。
減っているとは言え、また大小があるとは言え、農家はまだまだ多い。その中に、本当は稼げるなら続けたいと思っている人は少なくないし、さらに自分も農家になりたいという若者も少しずつ増えている。
足りないのは、彼らの仕事に方向を与える人だ。もちろん、農業改良普及員もいるし、JAの指導員もいる。だが、営農技術を教える人はたくさんいても(このことも問題なのだろうが)、マーケティングを間違い少なく教える人、買い手、製品の使い手の気持ち、ニーズを正確につかんで伝える人は、今多いとは言えない。
あるべき姿、行くべき方向を最も確実に示せるのは、品物そのものについて利害関係のある人だ。つまり、それは仲卸であったり、買い手そのものであったりする。長嶺さんも、買い手側の目線を持っていたから、出荷を適切にコントロールし、トレーサビリティや特別栽培という方向を示せた。
「国内農業を建て直そう」という威勢のよい号令をかけて農業に参入する一般の企業が増えているが、例えば流通、食品、外食企業ならば、圃場を手に入れて営農を行うだけが国内農業に貢献する道ではない。農家にとって、口うるさく注文の多いお客に徹することが、最高の農業振興の一つだと考えてはどうだろうか。
栽培をするなとは言わないが、一般に、それはあまり広げないほうがよいように見える。広くても数十a~1ha程度の実験農場を持てば、農家は「あの会社に新品種の実験をしてもらおう」という期待が持てるし、「あの人たちは一応栽培の現場を知っているから、嘘はつけないな」と“にらみが利く”ことにもなる。
ところが、それよりも広い圃場を持ってどんどん生産するということになれば、「あの人たちは、うちの敵。自分で作って足りない分だけ売ってくれというのでは、付き合いたくない」と思われるのが関の山だ。しかも、所詮は営農の素人なだけに、栽培に失敗もしやすい。すると農家は「それ見たことか」「レベルが低い人たち」とさんざんに吹聴するだろう。さらに、「進歩しなくても大丈夫。いままで通りやっていればいい」と、彼らの歩みを止める効果も持つはずだ。
※このコラムは「FoodScience」(日経BP社)で発表され、同サイト閉鎖後に筆者の了解を得て「FoodWatchJapan」で無償公開しているものです。