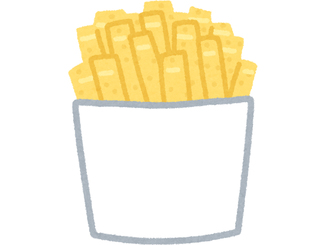新規就農希望者に向けて、「農業成功マニュアル」(翔泳社)という本を書かせていただいた。編集者からのリクエストは「全く予備知識のない人に向けて」というものだったので、農業、農家、農村の基本的な説明に少々多めにスペースを割いている。そのため、農家になろうと考えていない方でも、例えばコメや野菜の仕入れなどのために初めて農村を訪ねる、農家と会って話をするという場合にお役に立てる記述があると思う。12月3日発売なので、書店で見かけた折には手にとって眺めていただけたらと思う。
農業の取材を始めて早14年ほどが経つが、私はもともと外食産業の記者なので、農家に話を聞くときは、いつも飲食店との比較の中で理解してきたように思う。その初めの頃から現在に至るまでずっと感じていることは、外食産業の自由でオープンな空気だ。
これは個々の歴史観によって見方が違うものだが、私見では、戦前の農業は地主という資本家にして経営者が小作人という労働力を得て生産を行ったもので、善かれ悪しかれほかのビジネスに近い面を持っていた。戦後はその地主が国家によって退場を迫られ、代わって国や農協が広い意味での経営権を握ったと見ている。
その新しい体制の中で、戦前にもましてさまざまな規制が設けられ、「改良普及」や「営農指導」という名のもとに生産方法の立案や選択の自由が奪われ、系統流通によって使える資材が限られ、農家は消費地の情報から遮断された。そうして権利意識ばかり強く、マーケティングや顧客満足には頭脳と力をほとんど用いないタイプの農家を増やした。日本農業の国際競争力の低下というよりも喪失は、この体制と無縁ではない。従って、食糧(料)自給率の低下も、流通業や消費者のわがままだけによって起きている現象ではない。
そうした農業に対して、外食産業の自由さは際立って見えた。外食の産業化は、池田内閣の所得倍増計画以降に本格化していったが、その最初の頃から、行政からは見放された、誰も助けてくれない業種だったと見える。もちろん、実際には起業や事業継続のためにさまざまな支援や制度資金などがないわけではないが、農業に比べれば、外食産業は国からほとんど構ってもらえなかった業種と言っていいだろう。
何より、外食産業に行政サイドからの“改良普及”などはなかった。商品と業務の標準化や多店舗化のための戦略、それらによる産業化のための情報の収集と普及は民間が主導し、経営者たちは対価を支払って学習した。そのため、“弱肉強食”という耳障りの悪い言葉でもくくることはできるが、外食産業には、始める自由と、失敗も成功もある自由があった。外食産業が市場を拡大し、大きく成長できたのは、この自由さを抜きに理解することは難しい。
しかし、外食産業も大きくなるにつれ、行政とのかかわりは増えてきた。かつては農水省所管として落ち着いていたようだが、現在は厚生労働省や経済産業省もさまざまにかかわりを持つ場面が増えている。外食産業側にも、政治的な動きが見られることが増えてきた。もちろん、必要があってのことと言えるものも少なくないが、全体的に、かつてよりも保護や支援を受けたり、直接間接の規制を受ける場面は増えているように感じる。それがすべて悪いとは言わないが、外食産業が黎明期から持っていた自由さと、それぞれに孤軍奮闘であるがゆえのダイナミズムが失われることがないようにと願う。
また、せっかく作ってきたものとは言え、「外食産業」というカテゴリーを守ろうとする余り、個々の企業では戦略に自由度が失われてきたとも感じる。企業としての成長よりも、「外食産業」というカテゴリーの中での優位性維持にとらわれ、異業種との違いをことさらに強調したり、本来ないはずの差を設定して、実は優位でないことに目をつぶってしまっていないか。
例えば「中食」という言葉は、その定義と今後も使い続けるべきかどうかについて、再検討するべきだと考える。この言葉を広め、そういうものがあるかのように扱ってきたことにはマスコミにも責任がある。外食産業とマスコミと、それぞれで再考するべきだ。
私にとって「中食」なるものは、「食育」と並んで全く定義未詳、意味不明な言葉だ。いろいろな人の発言や記述からは、どうも弁当やそうざいを買ってきて家やオフィスで食べることやものを中食と言うらしいが、消費者の立場からは、「中食」という言葉は全く無効と思える。
例えば、ハンバーグを食べようと考える。レストランに行って「ハンバーグを」と注文すれば「外食」だし、スーパーで肉、パン粉、タマネギ、卵などをそろえて家で作れば「内食」だ。そこで、家で食べたいが時間がないというとき、レストランでテイクアウトしてくれば「中食」ということになるらしい。スーパーやコンビニのそうざい売場で完成品を買ってきても「中食」と分類するようだ。この場合、スーパーやコンビニの店内でレンジアップするのではなく、家でレンジアップしても「中食」と分類する人が多い。
ところが、スーパーやコンビニで、食品メーカーが作ったパウチされた完成品や冷凍食品を買ってきてレンジアップする場合は、多くの人は「中食」ではなく「内食」と分類したがる。これがよく分からない。食品メーカーのものは工場で作ったもので、レストランのものは店舗で作ったものと考えるのかもしれないが、レストランのハンバーグも、多くのチェーンのそれは材料を混ぜて成形したのは自社あるいは食品メーカーの工場だ。最近はチェーンだけでなく、中小の飲食店でもそうしたものを使っているところが増えているし、店によっては焼き目まで付いたものをレンジアップして出している場合もあり得る。
「どこで食べるか」だけを軸とすれば、本来考えられる分類は「外食」と「内食」だけだ。そこに、「誰が最終加工をしたか」という別な軸を含んだ「中食」という言葉を作り、「外食」と「内食」の中間にあるものと考えようとするから、3つの言葉の定義が壊れる。これは、外食、小売り、食品メーカーの三者が競合していることを見えにくくする有害な言葉だと、私は考える。本当はその三者で、「外食」と「内食」について協働したり、奪い合ったりしているだけなのだ。
統計を使って「中食市場が伸び、外食市場が縮小している」と説明されることがある。しかし、中食の定義がはっきりしない以上、この説明は外食の敗北感を緩和して聞こえるようにする効果はあるかもしれないが、これではどの業種がどのように支持されているのか、支持を落としているのかさっぱり分からない。外食産業は、まず「外食市場が縮小している」事実をしっかり受け止めた上で、「外食企業が内食市場でのシェアを増やしているか減らしているか」を見なければ、自社を評価して戦略を練ることもできないのではないか。
三つ巴の競争の中で、昨今の外食企業がなぜ劣勢に回ってしまっているのか。前回の「fresh」に関する話の続きで書くつもりだったが、今回もそこまでたどり着けなかった。次回までお待ちいただきたい。
※このコラムは「FoodScience」(日経BP社)で発表され、同サイト閉鎖後に筆者の了解を得て「FoodWatchJapan」で無償公開しているものです。