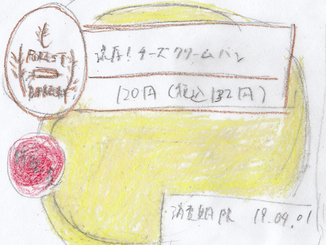同業者のことをあげつらうのはあまりやりたくないことだが、新聞、テレビ、週刊誌のむき出しのセンセーショナリズムには、いよいよぞっとさせられる。中国製冷凍ギョーザの中毒事件に関して、最初は「中国産」「農薬」「毒」が見出しに躍っていたかと思えば、この1週間は「テロ」の2文字を入れるのが流行になっている。現在の段階では、分別に欠ける、危険な言葉の使い方と感じる。
テロの可能性は否定しない。ただし、メディアでこの言葉を使うのにはもっと慎重であるべきだ。「テロ」「テロル」は、文字通り人々を“怖がらせる”強烈な言葉であると同時に、その定義は人や組織によって著しく異なるからだ。9.11以降、米国政府と同マスコミにはこの言葉を乱発する傾向が見られるが、「テロ」を喧伝(けんでん)することで“恐怖政治”を実現できる真の利益享受者は誰なのかには注意する必要がある。
定義は様々とは言え、「テロ」と言うには、最低限、犯人に政治的な動機、目的がなければならない。どんなに多数の死傷者を出すような事件でも、「怨恨」が動機であったり、いわゆる「愉快犯」であるなら、それは「テロ」とは言えない。例えば、和歌山毒物カレー事件の場合は、林眞須美被告が最高裁で争っている最中だが、犯人が誰にせよ、政治的な目的はあまり考えられず、テロではなさそうだ。グリコ・森永事件は犯人も意図も不明だが、直接的な意味での政治的意図はなかったと見るならば、これもテロとは言えない。
今回の中毒事件については、まだ犯人が分からないし、未だ犯行現場も特定されていない。政治的な目的を表明する犯行声明もない。確かに中国の政治と日本の政治に影響を与え、社会不安を引き起こし、日中国交の不安材料になっていく懸念もあるが、これで「テロ」と言っていいのかどうか。怨恨、愉快犯の可能性もまだあるし、複数のなんらかの事故の複合の可能性も理論的に完全には否定できていない。
それに目をつぶってあえて「テロ」と騒ぎ立てれば、日本と中国のそれぞれに確かに存在するであろう“日中関係の発展を望まない一部分子”が、手を下さずして目的を達成するということにもなりかねない。いや、すでにそうなりつつある。
「報道の自由」と言うが、そこには自ずから、自分たちがやったことがどのような結果をもたらすかに対する想像力と責任感が求められる。マスコミ各社には、例えば誘拐報道には慎重になれる能力があるのだから、このような新しい事象に対しても、思慮と分別を十分に発揮させるべきだろう。
日本でこのような一層不名誉な報道が過熱する中、案の定、中国政府は「中国国内の混入はない」との主張を始めたが、感情的な態度や文言で日本側を攻撃することはせず、冷静な印象を与えていることは、なかなかの達者と感じさせる。
さて、連日の報道でギョーザの映像と話題に浸かっていたら、ふとギョーザを食べたい気持ちが湧いてきて、休日には家でギョーザでも包むかと考えた。そこで目に止まったのが、ギョーザの皮が売れているという話だ。2月7日のMSN産経ニュースによれば、ダイエーでは事件が報道され始めた1月31日から4日間で冷凍食品の売上げが前年比30%ダウンする一方、ギョーザの皮の売上げは60%アップしているという。私もその売上増に貢献する口だったわけだ。
和歌山毒物カレー事件発生時には、イメージダウンを嫌ってカレー関連商品のCM放映を見合わせた企業があったようだが、よく調べれば、消費者が逆の動きを見せようとするデータも取れたのかも知れない。もちろん、事件では死者も出て、苦しんでいる方もいるので、何でもやっていいというわけではないが。「白い恋人」「赤福」の販売再開で売れ行きがよかったのも、ギョーザと同様に購買意欲をかき立てられた結果かもしれない。不祥事に際しては、関係する商品や企業のどの側面が傷つき、どの側面が無傷ないし逆にニーズが高まっているのかをよく検証する必要がありそうだ。
ただ、今回に関しては、外食企業と食品メーカーは、消費者のこの動きには注意するべきだ。自社の存在意義を問い直すメッセージとも受け取れるからだ。
元々、ファストフードをはじめとする外食産業は、手間はかかるが人々が好きなもので、しかもごちそう感のある、ハレに食べるメニューで伸びてきた経緯がある。日本では、古くは、そば、うどんがそうだ。ハンバーガーも、米国では休日に家族や親しい友人が集まって行うバーベキューの人気メニューだった。問題のギョーザも、中国では正月の料理という。
昔は、粉を使う料理は粉を挽くことから始めたので、穀物を粒のまま調理するよりはるかに手間と時間がかかった。また、肉でも野菜でも、細かく刻んで、混ぜて、こねるというのにも手間がかかる。だから、そのようなプロセスを要する料理の多くは、家庭では休日か年に何度かのハレの日に作って食べるものだったのだ。
これを外部化・専門化し、集中的に調理することでスピード化、低価格化を実現して、外食産業は伸びた。冷凍食品は、そうした外食企業の業務用として発達した歴史がある。
ところが、これら細かくして混ぜるというプロセスを経た食品は、何かの混入を目や舌で見付けにくい。その特徴を悪用したのが、以前あった韓国製“生ゴミギョーザ”だ。今回の中毒事件では、細かくした複数の原材料からできている食品は、毒物の検査に時間と手間がかかるとされ、そのことも報道されている。とすれば、今後この種のメニューは外食や冷凍食品で選ばないという消費行動にもつながり兼ねない。
このような加工度の高いメニューが内食化するということになれば、今後外食産業や冷凍食品で売れる商品は、肉や魚の切り身を調理したもの、カット、ボイルしただけの野菜など、加工度の低い単純なものへと追い込まれていく。一般に、そうした商品は付加価値が付けにくい、つまり利幅の少ないものだ。
それでも高い値付けでできる商品を売ろうとするなら、例えば銘柄肉、産地が限られる野菜、有機栽培など特殊な栽培による野菜といった、食材自体が価値を持つようなものに頼らざるを得ない。だが、これはつまり、産地がより利益を得て、外食産業や食品メーカーなどの加工業は利益を確保しにくくなるということだ。
安全、安心、危機管理を考えることも大切だが、この屋台骨に押し寄せる大波に気付き、鎮めることに、業界を上げて知恵を搾るべき時だ。
※このコラムは「FoodScience」(日経BP社)で発表され、同サイト閉鎖後に筆者の了解を得て「FoodWatchJapan」で無償公開しているものです。