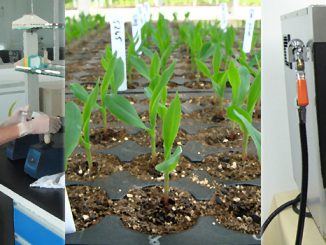イスラエルのPolysack Plastic Industries社が面白い調光ネットを販売している。施設園芸(ビニールハウスやガラスハウスなどの施設を使って野菜や花きなどを栽培すること)では、保温、遮光、遮熱などのために様々なカーテンスクリーンを使う。一般的なのは、白や黒のネット状のものだが、同社のChromatiNet(彩色ネットの意)はその名の通り、赤、黄、青、グレー、パールなどの色が着いている。
この着色はもちろんダテではない。ネットの色によってハウス内に放射される光の波長をコントロールし、例えば赤のネットでは植物の生長を促進、青のネットでは植物の生長を抑制する効果があるという。これらをうまく使えば、市場の動向をにらみながら作物の出荷を早めたり、延ばしたりということが可能になる。
従来、植物の生長の促進や抑制はケミカルでコントロールするか、カーテンを細かく開閉する操作などで行われてきたが、こうした着色カーテンは資材コストや労務費を削減する可能性がある。
同社ではまた、ALUMINETという、アルミ箔を編み込んだ遮光スクリーンも扱っている。アルミ箔を編み込んだスクリーン自体は珍しいものではないが、この商品の特徴は、アルミ箔付きの繊維にヨリをかけている点だ。一般的なものはアルミ箔付きの繊維を直線のまま編み込んでいて、太陽光の一部をハウス外にはね返して光の量を調節する。これに対して、ALUMINETは光を散乱させ、植物に様々な方向から光を当てることを目的としている。
夏の強い日差しから植物を守るために、従来の遮光スクリーンを使って光の量を抑えた場合、植物の上の葉に当たる光の量を最適化することはできるが、えてして下の葉は日照不足になりがちだ。そこで、散乱光を作るスクリーンをうまく使えば、太陽光線の束を同じ方向からではなく、さまざまな方向から当てることができ、上の葉と下の葉の働きの差を縮めることを期待できる。
これらのスクリーンは、本家イスラエルのほか、オーガニックに取り組む農家や生産コストに敏感な農家が多い欧米では導入が進みつつある。一方、日本の施設園芸ではまだ実用や試験の例は少ない。あるコンサルタントによれば、日本の場合、特に養液栽培(肥料成分をコンピュータ管理した水溶液で栽培する方法。水耕栽培)では、特に養液管理への関心は高いが、光などの環境因子は軽視されがちだとも言う。
養液タンクばかり見ていた目を天井に向けて視野を広げれば、経営の可能性が広がりそうだ。
光をより効果的に利用するというこれらの商品を見て、筆者が思い出すのは、宮城県岩沼市の農家、平塚静隆氏のことだ。氏は、レタスなどの野菜で売り上げを確保しながら、水稲の品種改良を手掛ける民間育種家でもある。「ごこくなみ」「ひより」といった酒米の開発で、酒造業界では知る人ぞ知る存在だ。
氏の育種戦略のポイントは、酒造好適米としての成分もさることながら、太陽光を効果的にキャッチする葉を持つ草型にある。戦後の水稲育種では、一般には密植(密度高く植えること)に向く直立・短桿(茎が短い)の草型を作ることが重視されたが、氏の場合は葉がある程度横に開き、太陽光線が葉面にまっすぐ当たるようにすることで収量を上げる“究極のイネ”開発に情熱を傾けている。
とは言え、トライアンドエラーを繰り返しながら選抜し、交配する地道な研究スタイルで、「一生かかって出来るかどうか分からない」。しかし、「中国では自分のイメージに近いものが完成している。近いけれども、私の目指す形と完全に同じではない。あきらめない」。
その平塚氏に、遺伝子組換えをどう考えるか尋ねたことがある。答えは、「そうした方法の必要性、重要性は理解する。しかし、それが育種のメジャーな技術になっていくことは心配」ということだった。
イネを観察し、選抜し、交配しをこつこつと繰り返す中では、予想外の結果も出る。だから、穂が出たときは瞬時にその新しい穂の意味を考察し、次の交配でどうなるかの予測を素早く立てる。平塚氏は、そうした伝統的な交配を繰り返す中でこそ得られる新品種があることを信じ、今後も重要な技術であることに変わりはないと考えている。そして何よりそのプロセスを楽しんでいる。
心配というのは、品種改良イコール遺伝子組換えと考えられるようになって、それに対してのみヒト・モノ・カネが集中すること。遺伝子組換えによる品種改良のプロセスにも交配のステップがあるとはいえ、もしも伝統的な選抜と交配による育種の技術がすたれ、やがて失われることになれば、農業の可能性を狭めることになりはしないか。
目指すものに対してアプローチは様々だ。生長の速度のコントロールには、ケミカルからのアプローチもあれば、光の利用を精緻化するというアプローチもある、ということも然り。重要なのは、そのどちらが優れているかではなく、持ち駒が一つ増えた、可能性が広がったということだ。
いわば、「あれかこれか」ではなく「あれもこれも」。昨今の日本人は、新しいものが古いものを倒すストーリーが大好きだが、あまりそのことに心を奪われて、視野とビジネスの可能性の幅を狭めていないかどうかには、農業にかかわるすべての人が常に、注意を向けているべきだろう。
※このコラムは「FoodScience」(日経BP社)で発表され、同サイト閉鎖後に筆者の了解を得て「FoodWatchJapan」で無償公開しているものです。