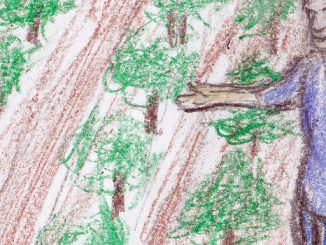現在、安全や安心な農産物と言った場合、多くの人がイメージするのは、“科学技術に頼らない”有機栽培などの栽培方法を行なっている農産物ということになるだろう。では、有機農産物は実際に安全・安心で栄養価が高いと言えるだろうか。
化学農業時代が有機栽培を生んだ
それを考える前に、まず有機栽培とは何かということを押さえておきたい。
かつて化学肥料は“金肥”(きんぴ)などと呼ばれていた。金で買う肥料、高価な肥料という意味だ。その名にたがわず大量に使用できるようなものではなかったが、高度成長以降は化学肥料の価格は下落し、ふんだんに使用できるようになった。
しかし、化学肥料に依存した結果、土壌中の有機物が減少し、土壌の劣化が進んだのである。かつては先に書いたような下肥など有機質主体の養分を含むものが肥料として利用されていたが、化学肥料を使うようになってそれら有機物を供給することが行われなくなったのだ。
畑の土というのは、砂や粘土の集積物ではない。試しに砂と粘土を混合してみればわかるが、この2つだけでは粘土に砂が混じるだけで、畑にあるような土にはならない。砂や粘土といった鉱物に、有機物(腐植と言う)が含まれることで、作物が育つ土壌になるのである。有機物がなくなれば砂まじりの粘土となってしまい、不毛の土地となってしまう。農産物を育てる土壌というのは、有機物をふんだんに含んだ土壌である必要がある。だから、畑の土壌を維持していくためには、作物という有機物をそこから奪い取る一方、何らかの形で土壌に有機物を還元することが必要なのである。
ここで言う有機物が何であるかを厳密に説明するのは難しいが、簡単に言えば炭素(C)が含まれるものだ。田畑の収穫物の残さ、家畜の糞尿や敷わら、山草、樹木の葉や茎も有機物だ。これらの中でも、とくに炭素が多く含まれればそれだけ有機物の量が多いことになる。炭素が多く含まれれば燃えやすいから、よく燃えるかどうかで考えれば畑に入れる有機物として有効かどうかを直感的に判断する助けになる。たとえば、作物残さ、山草、樹木の木の葉、茎などは燃えやすいが、動物の糞尿は比較的燃えにくい。動物の糞尿は作物に対する養分を大量に含んでいるため、肥料として使用するのには適しているのだが、土壌に有機物を還元して腐植を増やすという目的については、作物残さや木の葉ほどには有効とは言えない。
さて、化学肥料を使用することによって簡単に養分の供給ができるようになり、短期的には農産物の収量を増やすことができるようになった。しかし、それに頼った栽培を続けていると、土壌中の腐植は減っていき、いずれ作物が育ちにくい不毛な土壌になってしまう。そのことがわかってくると、化学肥料のみに頼った農業には限界があるということで、有機物の必要性が叫ばれるようになる。これが、いわゆる“土作り”である。
つまり、有機栽培というものは、化学肥料に依存しすぎて有機物の還元を忘れてしまっていることへのアンチテーゼとして生まれたのである。その直接の目的は土壌の生産性維持だが、畑への有機物供給源としての周辺環境を良好に保つことにも配慮され、環境保全型の農業と考えられるようになった。
DDTから始まった農薬開発競争
有機栽培のもう一つの特徴は、農薬を使用しない点にある。
農薬と言った場合、多くの方がイメージするのは、化学的に合成された化学合成農薬(以下とくに断らない限りは農薬と記す)だろう。おそらく、放射能問題を除けば、今日の消費者が農産物について最も気にするのはこれだろう。
では、農薬とはどんなものか。
歴史的には、地中海原産の除虫菊(シロバナムシヨケギク)に殺虫成分が含まれていることが発見され、それを加工して農薬として流通させたのが今日の農薬の始まりだと言われている。ちなみに、日本では上山英一郎という人が除虫菊を使って蚊取り線香を発明し、「金鳥」の商標を持つ大日本除虫菊の基となった。
その後、1939年にスイスの薬品問屋ガイギー社(後にチバガイギー、現ノバルティス)がDDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)に殺虫効果があることを発見したことが、化学合成による農薬開発の端緒となる。日本では進駐軍によるシラミ駆除で人の頭からDDTの粉を振りかける映像が有名だが、安価で効果も高かったことから第二次世界大戦後世界中に普及した。そして、「DDTに続け」とばかりに、化学合成による農薬の開発競争が始まった。
この農薬が危険視されるようになったきっかけは、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」(1962)という著作だったと言われている。DDTの残留性や環境・生態系への影響を訴えたこの著作に続き、日本では有吉佐和子の「複合汚染」
が1974年から朝日新聞に連載された。「複合汚染」は、農薬だけではなく公害問題などにも触れており、すでに各地で公害問題が発生していた日本で話題になり、環境問題も含めて、行き過ぎた科学万能主義に警鐘を鳴らした。
かく言う筆者も、連載時にではないが、この「複合汚染」を読んで、公害問題・環境問題などに興味を持った一人である。