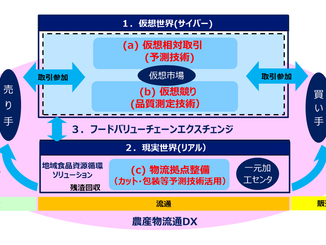日本で外食というビジネスが産業化したのは戦後、チェーンストア型のオペレーションが普及し始めた1960年代頃からあるいは1970年代頃からと言われています。しかし、多くの飲食店が事業として成立するほどに外食市場が発展し始めたスタートの時期は、江戸時代に遡ります。
庶民による外食市場形成がチップを廃れさせた
日本でその発展を支えた主人公は、一般庶民です。これは諸外国とは全く異なる歩みでした。
幕末から明治初期に日本を訪れた外国人は、日本の支配階級の暮らしが一般市民より質素であることに驚いたと言います。「武士は食わねど高楊枝」で、武家が粗食に耐えている一方で、町人たちはそばをすすり、天ぷらにかぶりつき、すしをつまみ、うなぎのさばき方・焼き方にいっぱしの評論を垂れていた。
メトロポリス江戸は、同時代の世界のどの都市よりも人口が多かったといいます。初期には男性の単身者が多く、日常の食事として外食が求められた。中・後期には世の中が安定し、女性も増えて、エンターテイメント産業が発達し、楽しみとしての外食も求められた。しかも、大工・職人が数日働けば長屋の家賃は支払えるということで、意外と可処分所得がある。そういう市民たちが、日本の外食市場を作っていった。
つまり、日本には300年からの大消費社会の歴史があるわけです。国王や諸侯や一部の富豪がサービス消費の中心であった世界各国とは全く事情が違います。中国料理、フランス料理、イタリア料理など、世界で尊ばれる料理のほとんどは、為政者、高官、富豪の接待や娯楽として発達した部分が大ですが、日本の外食で親しまれている料理のほとんどは、市民に提供され、市民が磨き上げてきた料理なのです。
その流れが、明治、大正、昭和と続き、今日に至っているわけです。いわば、提供者と喫食者との間に、決定的な身分的な上下がない。全くなかったわけではありません。印象も含めて本格的に身分差が消えたのは戦後の発展のプロセスの中であったでしょう。しかし、態度の悪いお客がいれば放り出されるぐらいには、お客と店の間にある種対等な関係があるのが、日本で発達した外食ビジネスとは言えるでしょう。
そのような市場では、貴人が庶民に施しをするとか、不案内な“未開地”にやって来た富豪が金にものを言わせて珍稀や快適を手に入れるとか、アメリカの成金青年のように見栄を張るとか、そういう形の消費はなじまなかったのだと考えられます。一般庶民の消費が発達し、膨張するプロセスで、チップや心付けの制度・習慣は廃れていったのでしょう。
とすれば、逆に、チップのある国・地域というのは、日本のように消費社会がまだ十分発達していない社会と見ることもできます。
もちろん、江戸時代にも、チップや心付けがなかったわけではありません。とくに、花柳界、遊郭にはそれがありました。ただ、落語など聞いていると、遊郭で遊ぶ人というのは、どうもあまり喜んで心付けを渡していない。店に言われるので、それが作法だからというので、仕方なく“払ってやる”ものだったのです。
ところが、町場の屋台や飯屋や居酒屋ではそうでもない。あるいは時代が下ってどの店でも、そういう制度・習慣はないということになってみると、何か渡さずにはいられない。それがお客が発する「ありがとう」「ごちそうさま」ということでしょう。
あるいは、人によってはなじみの店に“手土産”を持って行くことがあります。それも、たいていはその場限りでなくなってしまうお菓子など安価な食べ物が多く、高価だったり、現金や換金性があったり物品としての価値が持続したりするようなものでないものです。舞台用語で言う“消えもの”です。出した途端に相手の体の中に入って消えてしまうという意味では、食べ物は言葉に近い。それは利益供与ではなく、話題作り、関係作りです。
同じことを、店の側がすることもあります。店のレギュラー商品ではないもの、しかも、「はい、飴ちゃん」のように、そのものの価値としては取るに足りないようなものを、「たまたま手に入ったから」とかと理由をつけてお客に配る。こういうものは、価格が明示された商品と金銭とのやりとりだけでは実現しにくい、お客と店の関係づくりに役立つものです。
高客単価で来店頻度が下がるのは金勘定からなのか?
さて、少々脱線しましたが、チップ、チャイ、心付けの制度・習慣が廃れた今日の日本の消費社会で、飲食店やホテルのサービス料の制度が、お客にどう受け止められるものか、改めて考えてみましょう。
サービス料を設定している飲食店やホテルは、一般に“高価な”店です。具体的には、客単価は5000円以上、2万円とかそれ以上とかであることが多いでしょう。仮にサービス料を設定しない店でも、その程度の客単価の店には共通の特徴があります。利用頻度が低い、ということです。たとえばある1組のお客が年に数回、あるいは数年に1回とか。したがって、近隣住民だけでは回りませんから、所在する都市全体あるいは日本全体あるいは世界全体が商圏ということになります。すなわち、大商圏型ないしは超大商圏型の店であるということです。
客単価が一定レベル以上に高額であると利用頻度が低くなることの一般的な説明はこうです――一度の支出が可処分所得に対して大きいと何度も利用できない。可処分所得が100あるところ、10の支出は10回できる、1の支出は100回できる。しかし、50の支出は2回、100の支出は1回しかできない、ということです。
とは言っても、人というもの、それをいちいち計算してそのように行動しているわけではありません。可処分所得に対して一度の利用額が高額であれば利用頻度が低くなるというのは、ある意味結果論でしかないのかもしれないのです。お客のその都度その都度の行動は、必ずしも金勘定だけに支配されているとは言い切れない部分があります。
では、なぜそうなるのか。
(つづく)