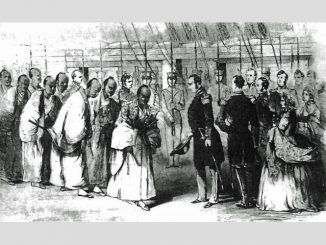今回のシリーズ「帝国ホテルのマウント・フジ」の執筆が一段落ついたころ、筆者は箱根に向かう電車の車中にいた。町田を過ぎ、海老名を超えると緑の中に行儀よく並んだ一戸建て住宅が並び、駅前もコンビニが点在するばかりで森や畑が増えてくる。
知られざるホテル内部の競技会
箱根湯本の湯本富士屋ホテルで、富士屋ホテルチェーンの各ホテルから選抜された5名のバーテンダーによるカクテル・コンペティションが行われると聞いたのは、その半月ほど前だった。外部に公開したことはないという。それを聞いて、昨今日本のホテル・バーテンダーが次々に海外に打って出ていっている中、それとは全く別の世界で研鑽に励んでいる彼らの姿に興味を惹かれ、関係筋に何とかとお願いしてそのコンペを見せていただけることになった。
去年、延々数カ月にわたって読んでいただいた「日本人の知らないジャパニーズ・カクテル/ミカド」のことを、今一度思い起こしていただきたい。
大航海時代になって、かつてヨーロッパでは黄金伝説としてしか語られることのなかった“謎の国ジパング”から、さまざまな文物がもたらされるようになった。欧米の人々は高度な技巧を凝らした精緻な工芸品に驚嘆の声を挙げ、大胆な方法で描かれた浮世絵はコレクター垂涎の的となって、世界的に有名な印象派の画家たちに大きなインスピレーションを与えた。
その後19世紀になってようやく、この神秘の国の門戸を開かせたのは、新興国のアメリカであった。そのときの日米双方にあったさまざまな思惑と、日本には“閉鎖された社会で独自の発展を遂げた文化”があったこと、そして日本のクラフトマンシップが存在していたことが、世界初のカクテルブックに国名を冠した初のカクテル「ジャパニーズ」が掲載されるきっかけになったと言えるだろう。
外資系を中心とする国際的なカクテル競技会で多くの日本人が活躍していることは広く知られているが、富士屋ホテルチェーンのバーテンダー事情に当たってみると、彼らはこれまで積極的に外部との交流を求める道を取らず、独自にスキルアップする方向で独自の進歩を遂げてきた。そのことが、何とはなしに鎖国時代に独特の文化を花開かせた日本を思わせるのだ。
なお、高いレベルを誇りながら外部との交流を避けているかのようにひっそりと活動しているホテルは富士屋ホテルばかりではない。文筆家にはバー好きが多いと聞くが、彼らが原稿の締め切りに追われ、出版社によって“カンヅメ”と称する軟禁を受ける際、よく利用されるのが山の上ホテルだ。このホテルも同じ伝統を持つ。
最新流行のリキュールやカクテル、派手なパフォーマンスとは無縁なものの、神田の隠れ家的なホテルの一角で出される一杯には多くのファンがついていることは、それが単なる頑迷さによるのではなく、ホテルが個性を育てるための一つの選択肢であることを示している。
華やかな世界の晴れ舞台とは全く別の、部外者の目には触れないカクテル・コンペティションとはどのようなものなのか。のどかな田園地帯を箱根湯本へ向けて疾走する電車の中で、筆者の期待は高まっていった。
公開競技会とは異なる厳しさ


快活な外国人観光客や、団体旅行の日本人客で賑わう箱根湯本駅から、湯本富士屋ホテルへと向かう。外部向けの大会ではないため、フロントで聞いた会場の外には看板一つ掲げられていない。恐る恐るドアを開けてみると、富士屋ホテルチェーンの各ホテルからこの日のためにやってきた5人の出場者が真剣な表情で段取りを確認している姿が目に入った。
心配そうに見守る先輩や上司と、今回スピリッツを提供したサッポロビールの関係者を除けば、部外者は本当に筆者一人しかいない。実技を行うためのテーブルに向かい合う形で10脚ほどの椅子と長机を並べた会場は、日頃の華やかなカクテル競技会を見慣れた人間なら殺風景とさえ感じる風景だ。
「それじゃ、始めます」という司会役のホテルマンの一言で競技が始まった。審査員は、だいたい二十代の若い出場者の上司に当たる人たちばかりだから、満場の観衆の前とは別の緊張で手が震えている出場者もいる。そうかと思うと、一つひとつの所作にホテル・バーテンダー特有の「タメ」(ポーズ)を作る出場者もいる。
通常、カクテルの競技会では、審査員が試飲しなければならない数がかなりのものになるため、大抵は1点につき一口で終わるものだが、半分以上を飲んでしまう審査員もいる。そのため、筆者には「こういうことに慣れていない人たちが審査員になっているのだろうか?」といぶかる心もきざしたのだが、一連の実技が終了したときの審査員の質問を聞くや、そんな疑問は覆されてしまった――原価計算ミスの厳しい指摘(提供価格1200円、原価率20%が出品カクテルの条件)、同じホテルでありながらシェーカーの振り方が各者各様であることへの疑問、「決めのポーズは採点対象になるのか」「無駄なステアでガスが抜ける」といった問いや叱り、さらに「僕はこの味が好きじゃない」「酸味がキツイ」といった意見もあり、果ては「キャリア不足が味に出ている」と言われて泣きそうになる出場者もいる。一人ひとりの出場者にすべての審査員がかける真剣な質疑の時間は30分を大幅に超えた。
秘めたる研鑽
1位から5位までの結果が発表された後、出場者に話をうかがった。全く畑違いの中華部門で朝9時から夕方6時まで働きながら、その後泊まり込みで練習した出場者がいた。先ほど一つひとつの所作にタメを作っていた出場者は、仕事が終わった後、他のホテルのバーに何度も通ってそれぞれのポージングを覚えたという。
彼らの努力は決して一般客の目に付くことはない。その後調べたところ、その他にもリーガロイヤルを初め、ホテル内部で行う内輪の競技会で技術の研鑚に励むケースは珍しくないという。バーテンダーと言うセグメントで見た場合、世界大会への出場や各種バーテンダー団体が開催する行事への積極参加という形での活動が記録に残りやすいのは事実だが、それとは別に、多くのバーテンダーが目に見えないところで日本のカクテルのレベルを維持・向上するために日々研鑚を積んでいることを知った日だった。
富士屋ホテル中興の祖、山口正造は、バーテンディングを他の業務と同様に「ホテルマンの一つの技能」として捉えていた。その富士屋ホテルの伝統は、現在も引き継がれている。今回の競技会で専門的な質問をした富士屋ホテルの役職につかれている方々の多くは、自らもかつてはカウンターに立ってシェーカーを振っていたという。
日本の会社では叩き上げの人間がトップに登り詰めるため、役員報酬が海外に比べて低い……という経済紙の記事を読んだ。海外では華麗な履歴を持つ、ごく一部の選ばれた人たちが巨額の報酬でスカウトされて会社のトップになる。契約期間が終わると、それまで積んだキャリアを武器にして高額の報酬を準備する別の会社に移っていくので、日本の役員報酬とは概念が異なる――確かそんな趣旨だった。そのことには、日本と海外との、働き方の概念や技能の磨き方に対する考え方の違いが現れているだろう。
外部に知られることなく、外部から隔絶された場所で人知れず研鑽に励む日本のホテルのバーテンダーたちには、山口正造時代から変わらない日本のホスピタリティーがあるのかもしれない、そんなことを感じる一日だった。