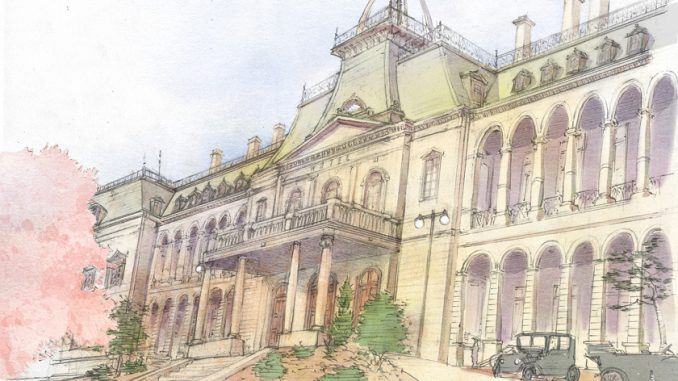
さて、目先を変えて帝国ホテル版マウント・フジのレシピから探索を続けよう。
クリームとレモンジュース
ミキシング・グラスに氷とベルモットを入れて掻き回し、ジンを加えたものをカクテルグラスに注いでオリーブを一粒浮かべさえすれば、味の善し悪しはともかく、マティーニは出来る。ウイスキーにベルモットを注いでチェリーを飾ればマンハッタンと呼べるカクテルも出来ないことはない。必要なものは洋酒と氷である。
ところが、帝国ホテル版のマウント・フジは、ジン、マラスキーノの他に、卵白、パイナップルジュース、レモンジュース、クリームという“生もの”が加わる。
卵白に関して言うと、海外では日本と衛生基準も食文化も異なるので、現在でも欧米人は生卵を食べないことは知られている。ところが、実はカクテルではエッグ-ノッグというタイプのものをはじめ、いくつかのフィズやサワーなどで生卵が頻繁に使われている。
とくに帝国ホテル版マウント・フジに使われる卵白については、当時の冷蔵設備事情との兼ね合いがうかがわれる。
当時のホテルには氷式冷蔵庫があったが、この場合、生クリームの品質保持には難しさがある。衛生状態がよく密封パックで流通する今日でも、生クリームの賞味期限はせいぜい数日、開封すれば1日で使い切るのが原則だ。まして、急冷装置など付いていない昔の氷式冷蔵庫で生クリームを管理して、カクテルを調整するたびにドアを開け閉めしていたらどうなるか。
そこへいくと、鶏卵は卵殻に傷さえついていなければ保存が比較的容易である。今日のようにスーパーサルモネラなどの危険がクローズアップされる以前は、鶏卵を常温で管理することはよくあった。10~15℃前後で保存できれば、鶏卵は夏場で2週間、冬なら1カ月は保存できる。
だから、カクテルの口当たりを滑らかにするものを使おうとした場合、生クリームよりも鶏卵のほうが都合がよいということになる。
しかし、これにクリームとレモンジュースが加わるとなると、カクテルの難易度は一挙に上がってくる。
現在帝国ホテルに伝わっているレシピに従うと、クリームと卵白に含まれるタンパク質は、レモンの酸で凝固する可能性があるし、当時ホノルルから取り寄せていた瓶入りのパイナップルジュースにも酸が含まれている。
たとえば大正13(1924)年の世界一周旅行団が、帝国ホテルでの歓迎式典に全員ではなく仮に半分が帝国ホテルにやって来たとしても(当時の世界一周旅行団は受け入れ側のキャパシティの問題もあって、半数が現地遊覧している間、残りの半数は船でその後を追っているといったことが珍しくなかった)、その人数は100名近くに及ぶことになる。
サマリア号でもエンプレス・オブ・カナダ号でも構わないのだが、これだけ大量のゲストがいちどきにやって来たとしよう。彼らの人数に式典の来賓を加えた数のカクテルを作って並べるには時間がかかる。となれば、1杯だけ作って出すのも難しいのに、下手をすると挨拶が終わって乾杯するときにはグラスの中で分離していたということにもなりかねない。きわめてリスクが高いカクテルと言える。
初めて来た女性客の「何か、私に合ったオリジナル・カクテルを」といった注文に、平成のバーテンダーは苦肉の策で“果汁を使って炭酸で割った”ような即興の“オリジナル”をしばしば作る。帝国ホテル版マウント・フジは、そういうものとはわけが違うのだ。つまり、事前に周到な準備と試行錯誤を重ねて作られたことが想像できる。
しかし、そのレシピから当時のバーテンダーが苦心して調製したことは推察できたとしても、それだけではこのカクテルがどのようにして生み出されたものかを明らかにすることにはならない。
富士屋ホテルとの出会い
そこまで考えて行き詰まったのが、10年ほど前のことだった。そんなある日、筆者は銀座を歩いていた。当時まだ銀座にあった「イエナ」という洋書店で、目が飛び出るほど高いアブサンの本を買った日だった。後にも先にも洋書屋で値切ったことなど、このとき以外になかったのだが、フランス語の本で2万円近かったと記憶している。表紙がかなり破れていたこともあって、どうにか1万円で売ってもらって、その帰宅途中の出来事だった。
「イエナ」の担当者の親切に感謝しつつ、滅多に来ない銀座だからと街を散策していた筆者の目が、はるか向こうにぼうっと浮かび上がる「FUJIYA HOTEL」と書かれた白いビルを捉えた。
広尾にある都立中央図書館で見つけた「新版世界のカクテル大事典」という、全3冊で3万円以上する大冊がある。この本は各カクテルブックのレシピを列挙した研究書に性格が近く、通常のカクテルブックとは趣を異にする本なのだが、それによればマウント・フジのレシピが7つあり、2つはラムベースのJBA版で、あとの5つはジンベースの帝国ホテル版である。ところが、その帝国ホテル版のレシピの一つに「八重洲富士屋ホテルのオリジナル・カクテル」と注記があったことが筆者の脳裏によみがえった。
初めてそれを見た頃は、「また、どこかの温泉ホテルが勝手に帝国ホテルのものをパクりでもしたんだろう」としか思わず、そのまま読み飛ばしていたことも思い出した。
幸い、懐には「イエナ」が割り引いてくれた残金もある。「一応、裏だけでもとっておこうか」――そんな、ドラマに出てくる安いコートを着た刑事のような独白を呟きながら、筆者は足を東京駅の方向に向けた。
そのとき、マウント・フジは注文したはずだが、バーテンダーと何を話したかは覚えていない。次に覚えているのは翌日に掛かってきた電話だった。富士屋ホテルの広報だと名乗った担当者が、見せたい資料があると言う。
数日後、筆者の自宅に送られてきた昭和14(1939)年の富士屋ホテルのワインリスト(ドリンクメニュー)には、まぎれもなくマウント・フジが記載されていた。





