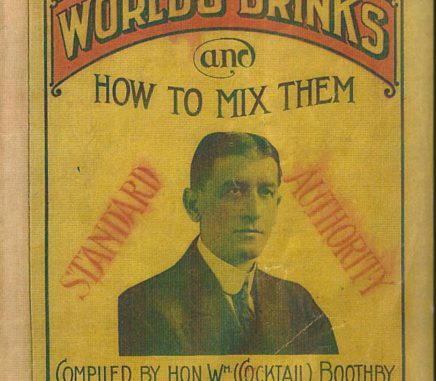
再現したジャパニーズ・カクテルの香りは醸造酒の持つ複雑な香りを持ち、最初の口当たりも紹興酒のそれに似たものを感じさせた。ただし、近さを感じさせる一方、すれ違う部分もある。そこで筆者が気になったのは、ベースとなるブランデーの質だった。J.トーマスのものは、最高級のブランデーが使われていた可能性が高いのだ。
同窓会で久しぶりに会った恋人のように
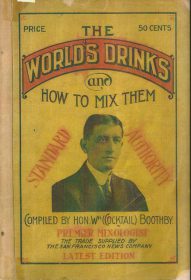
写真を撮った後、おそるおそるグラスを持ち上げる。
香りに関しては、紹興酒特有の「麦わら香」「青畳の香り」はないものの、醸造酒系で感じられる複雑な香りに近いものがある。
オルゲートはベンズアルデヒド(benzaldehyde)という成分がアマレットと共通なので香りは似ているが、アマレットとオルゲートを嗅ぎ分けると明らかに違いが感じられる。うまく表現できないのだが、アマレットはアジア的な花をイメージさせる香りはするものの、「ヨーロッパ人が想像するアジア」的な感じを超えることはない。ところがオルゲートは一説に中央アジアが原産地とされるせいでもあるまいが、「アジアの香り」をアマレットより遙かに強く感じさせる。なんというか、中国のなかでも西側の遊牧民族で賑わうバザールの羊肉と汗と砂埃の混じる街の臭いを彷彿とさせる。
口に含んでみる。オリジナルの指定はステアなので、オルゲートは少し底に残る。この状態で紹興酒と比べると、まず口当たりのアルコール度数が両者かなり近接していることに驚く。ジャパニーズ・カクテルはかなりオルゲート由来の甘さが強く、先述ブースビーのカクテルブック「The World’s Drinks And How To Mix Them」にはわざわざ「冷水を添えて出す」と注意書きがあるほどなのだが、慣れてくるとさして甘さは気にならなくなる。
紹興酒に砂糖を入れてみると口当たりはジャパニーズ・カクテルに似てくるのだが、味わいは逆に遠ざかってしまう。香りの点でもそうなのだが、紹興酒の麦わら香の中から出てくる西洋的なナッツのニュアンスをジャパニーズ・カクテルには求められず、逆にジャパニーズ・カクテルはオルゲート由来の香りにビタースの漢方薬系が混ざって天山山脈の高原を吹き抜ける風さえ思わせるほどアジア的なのだが、紹興酒からは離れていく。
傍目から見れば相思相愛なのに、細かく嗅ぎ分け、ビタースや砂糖を加えていくと近付きはするものの決して交わらない、悲しい恋のような感じなのだ。
ジャパニーズ・カクテルはブランデーが主体だから、あれこれ足して試しているうちに筆者の嗅覚と味覚も怪しくなってくる。しかし、紹興酒に砂糖を加えたり、ビタースやレモンをジャパニーズ・カクテルに足したりして比較しているうちに、両者の違いは些細なものとなり、同窓会で久しぶりに会った恋人のように徐々に近づいてくる。
オリジナルはフィロキセラ禍以前のブランデーを使っていた
4カ月を超える長丁場となったジャパニーズ・カクテル探索の旅が終わりに近付いた頃、筆者の数少ない友人の一人から大きな段ボールが届いた。
実はJ.トーマスのオリジナルに近づけるためには、完全復元をとりあえず断念したビタース以外にも引っ掛かっていることがあった。1860年代にフランスを襲ったフィロキセラ禍以前のブランデーを使っていたことだ。グレードも当時、ニューヨークのセレブが集った1860(万延元)年のパレス・バーの客層と品ぞろえを考えると、当時望み得る最高級のブランデーが使われていた可能性が高い。筆者が試していた、いつ開封したかも覚えていないアルマニャックで大丈夫だったのだろうか。
2012年10月にイギリス・ロンドンで発表され、ギネス級の価格で話題になったカクテル「サルバトーレの伝説」は、コニャック(1778)、キュンメル(1770)、オレンジキュラソー(1860頃)、アンゴスチュラ・ビタース(1900頃)と、どれもがサザビーズやクリスティーズ級のオークションに出しても恥ずかしくない年代ものの酒を使ったために、日本円で1杯69万円するそうだが、そこまでは行かなくとも、もしかしたら普及品のブランデーでは出ない味が上物のコニャックなら出るかもしれないという疑念は復元作業をしている間中、ずっと頭から離れなかった。
そんなときに友人から「部屋の荷物になるから引き取ってくれないか」と届けられた洋酒の段ボールの中に、1970~80年代のクルボアジェ社のナポレオンがあった。当時の価格で25000円だから、これならトーマスさんも復元の結果に文句は言うまいと思い、こんな機会でもなければ高価なブランデーを開ける縁も“円”もない筆者は、エイッとばかりに目をつぶってクルボアジェの極上コニャックの封を切った。百円ショップの計量スプーンで作る所作も、試作を繰り返した今ではお手のものだ。
恐る恐る口に含む――思えば4カ月を越える長期戦だったが、友人の助力を得て納得のいく形で結末を無事に迎えることができ、筆者は安堵のため息を漏らした。




