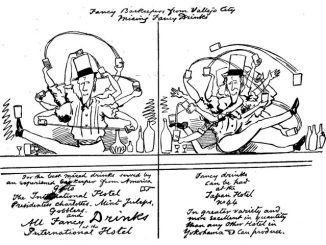エイダ・コールマンの例にならい、日本の当時の一流ホテルに女性バーテンダーの名を探す。もしそこに名前が見つからなければ、探索は一挙に難しくなる。年号が昭和に変わって全盛期を迎えたカフェー、そこでおぼつかない手つきでシェーカーを振っていた「女給」という存在があるからだ。それでも見つかったある女性は、確かな腕を持つ名バーテンダーであったはずだが、その後の消息はつかめなくなってしまう。
横浜グランドと帝国ホテルに該当者なし
世界初の女性バーテンダー、エイダ・コールマンの例をそのまま戦前の日本に当てはめるなら、その人の職場は当時バーテンダーにとって金字塔だった横浜グランドホテルか帝国ホテルということになる。このいずれかのバーで働くバーテンダーに女性がいれば、話が早い。
まず大正13年の関東大震災まで営業していた横浜グランドホテルに在籍していた日本人バーテンダーを見てみよう。高橋顧次郎を筆頭に浜田晶吾、秋田清六、本多春吉といった戦前日本のバーテンダーたちをリードしていたそうそうたる名前が並ぶが、女性の名前は見当たらない。浅倉進次郎、玉田芳太郎、藤生和邦、日山理策を擁する帝国ホテル・バーテンダーの陣容も同様だ。
さて、困ったことになった。
歴史に残る世界初の女性バーテンダー、エイダ・コールマンに関しては、「サヴォイの二代目チーフバーテンダー」という有無を言わせぬ“鑑定書”が存在する。ところが、当時の日本でホテル関係での手掛かりを失うと、これが簡単な話ではなくなる。
なかでも厄介なのは、時代が大正から昭和に替わった時期に「女性バーテンダー」を売り物にするカフェーが珍しくなかったことだ。
戦前昭和の“ガールズ・バー”
唐突だが、読者の方々は“ガールズ・バー”というところに行かれた経験はおありだろうか。カウンターの中に若い女性が並び、おぼつかない手つきでシェーカーを振ることが売り物だそうで、キャバクラより安く飲めることもあって、彼女たちとの疑似恋愛を楽しみに来る男性客が引きも切らないという。
利にさとい戦前の酒場経営者たちも考えることは同じだった。
まずその前段階として、東京朝日新聞に「愛嬌を忘れて生まれてきたらしいエプロンの少女」(1911年)と評され、客のくわえた煙草にマッチで火をつけるのが唯一のサービスだった大正時代の「カフェー・ライオン」や「カフェー・プランタン」の、ある種牧歌的な流れがあった。
これを一挙に愛嬌と色気を前面に押し立てて市場を席巻したのが、大阪から進出してきたカフェーだった。女給にシェーカーを持たせてカウンターに並べれば人気が出るに違いない。そう気付いた大阪カフェーの一つ「ユニオン」が断髪洋装美人を集めてシェーカーを振らせれば、東京でも昭和8(1933)年には20人からの女給が交替でカウンターに立ってカクテルを作る「ブラボー」が出来るといった状況となる。
人気女給を前面に押し出すことで、東京・銀座のみならず日本中を席巻したいわゆる大阪カフェーについては、「日輪」「赤玉」「銀座會舘」等々、洋酒を究める左党にとってはある意味邪道な存在ではある。しかし、戦前洋酒史を語る上で避けるわけにはいかない存在であることもまた事実なので、後日稿を改めて詳述したいが、ここではひとまず昭和初期にはすでに現在のガールズバーに近い流れが大阪からやってきていたことを示しておく。
つまり、日本初の正統女性バーテンダーを探すためには、ただでさえ資料が限られている戦前の酒場関連資料で見つけてきた数少ない「シェーカーを振る女性たち」を、さらに虫眼鏡で探して“本物”かどうかを選り分ける作業が余計に加わってくるのだ。
バーテンダーを一つの職業としてとらえる真面目な女性が戦前皆無だったわけではない。「文学時代」昭和6年6月号の座談会で、カクテル修業をしていたという女性が発言しているし、明治44年にカフェー・プランタンを開いた松山省三が、昭和に入って神楽坂から銀座に戻ってきたとき、「プランタン」(フランス語で「春」)の裏に「モデルのチャコさん」を店長にしたバー「ドートンヌ」(同「秋」)を出したことも記録には残っている。
しかし、前者は大阪「堂島クラブ」の前身でバーテンダーを勤めたらしいことまでわかったものの、名前が定かでない。「モデルのチャコさん」も名を貸しただけの店長なのか、バーテンダーとしてカウンターに立っていたのかまではわからない。
数寄屋橋「カストロ」の姉妹
決め手に欠ける閉塞感をいっきに吹き飛ばしたのは大正14(1925)年の新聞記事だった。これによれば(新聞名と正確な期日はこのシリーズを単行本として上梓した際に明かす)、その店は日本橋数寄屋3丁目(現在の日本橋2丁目)の地下にあるバー「カストロ」で、宮垣みね子(28)とし子(21)姉妹が2人で営業していた。
少し長くなるが、姉のみね子の話を「洋酒の變り壜に美人姉妹の店開き」と題した新聞記事から引用しよう。
「今度姉妹で店開きし『私の處は主にカクテルですが』と大にカクテルの効能を説く(中略)カクテルの家庭化――私はそんな講習會でも開きたいと思いますが、今は暇がないので思うばかりで居ります」とカクテルへの思いを熱く語り、さらに外国人と日本人のカクテルの注文の仕方の違いにまで言及していた。

驚くことに、彼女が持つ確固たる自信は聞きかじりの耳学問や書籍で得た知識によるものではなかった。彼女がカウンターに立つのは「カストロ」が初めてではなく、なんと拙稿の第一シリーズ「モダン・ガールは何を飲んでいたのか」で尾竹紅吉に五色の酒を出した「メイゾン鴻之巣」で彼女は働いていたことまで新聞に書かれていたのである。
鴻之巣時代の彼女の様子を、当時酒場を渡り歩いていた酒場評論家、今でいうとグルメリポーターの酒井眞人は昭和4(1929)年の「カフェ通」でこう評している。「京橋に移ってからでさへ、中々この店(鴻之巣)は爽やかな風格があってよかった。女主人(宮垣みね子)も美しければ、ウェイトレスも若くて気品があった」
昭和5(1930)年に出版された「COCKTAIL’S 調合法四百餘種」はさらに明快に、「此の鴻之巣こそ其の當時女バーテンダーで有名なものであったのである」と断じている。
宮垣みね子が鴻之巣でバーテンダーを始めたのは大正10年前後(※)であり、「カストロ」も姉妹2人だけで営む小さな店とは言え、バーのカウンターを任されるだけの技能が彼女にあったことをこれらの資料は雄弁に物語っている。
資料に現れない宮垣みね子

これほどしっかりとした足跡を残しているにもかかわらず、彼女本人の消息は大正から昭和に入ってぷっつりと途絶えてしまう。鴻之巣で修業し、日本橋のバーのカウンターを一人で仕切っていたキャリアからすると、その後のJBA(日本バーテンダー協会)関連資料に名前が出てきても不思議ではない……というか名前が出てこない方が不思議なのだが、昭和4(1929)年のJBA発起人名簿にも、筆者が最近になって入手した昭和5(1930)年のJBAの会員リストにも、彼女の名前を見つけることはできなかった。
鴻之巣の主人奥田駒蔵の孫にあたる奥田万里の著書「祖父駒蔵と『メイゾン鴻之巣』」によれば、酒場(バー)は4階建てのビルの1階にあり、曲木細工の椅子に円いテーブルが数脚、冬にはだるまストーヴが赤々と燃えており、カウンターのバックバーに洋酒瓶がずらりと並んでいたという。
宮垣がシェーカーの音を響かせてカクテルを調製していた「鴻之巣」と「カストロ」の存在を指し示す数少ない資料は、大正時代の女性バーテンダーが幻想ではなかったことを後世に伝えている。
※鴻之巣は日本橋小網町鎧橋際から日本橋木原店(きはらだな)、京橋南伝馬町へと移っている。酒井眞人の文章と重ね合わせると大正9~12年頃が宮垣が鴻之巣に在籍していた期間と推定される。