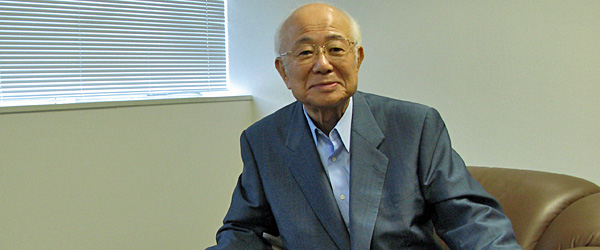
【味の素特別顧問歌田勝弘さんへのインタビュー】味の素株式会社(以下、味の素社)第7代社長(1981~1989年)を務めた歌田勝弘氏に味の素社の歩みを聞き、永続するブランドと企業活動の秘訣を探った。
第2回は、業界に先駆けて設置した広報室がどのような役割を担い、どのような活動を展開してきたかを聞いた。
インタビューでは、編集部からの簡単な質問に対して、歌田氏は詳細な内容を一息に話されたため、聞き書きの形で記した(カコミ部分は齋藤)。
社会とのかかわりを担当する専門部署
オルニーの論文発表に対して、味の素社は科学者に検証を求める一方、消費者への情報発信も開始した。ただし、それは企業から社会への一方通行のものではなく、社会と企業とで意見・情報を出し合い、良好な関係づくりを目指すものであった。それを担当したのが、当時国内企業に見られなかった新しい部署、広報室である。
他に先駆けて広報室を設置
味の素社が広報室を作ったのは、そうした困難が始まって間もない頃、昭和45(1970)年1月のことです。これは副社長直轄の組織です。
今日でこそ、どこの会社にも広報室というのはあるものです。パブリックリレーション(public relations ※)という概念や活動も普通になりました。しかし、その頃の日本では、まだどの会社にも広報室というものはありませんでした。広報室の設置は、味の素社が先陣を切ったと思います。
きっかけとしては、商品の安全性を伝えたいということだったわけですが、広報室設置のときに社内で盛んに言っていたのが「ツー・ウェイ・コミュニケーション」ということでした。こちら側から言うべきことは言う一方、消費者側からもいろいろな意見を聞いて来なさいということが命じられた。
食の安全問題というのは、みなさんが気にしている問題で、みなさんが本当のことを知りたがっている問題です。けれども、本当のことがなかなか伝わっていないものです。みなさんが知りたいものが何かをつかみ、それに対して正確な知識を常に発信していくことが大切です。
※編集部註:パブリックリレーションは社会との望ましい関係づくりのための活動を言う。public relations の略語PRは、今日しばしばプロモーションと混同されるが、パブリックリレーションと販売促進(SP)は全く別の活動である。
参考:「パブリックリレーションズとは」(日本パブリックリレーションズ協会)
http://www.prsj.or.jp/shiraberu/aboutpr
原料訴求キャンペーン
また、昭和57(1982)年からは「原料訴求キャンペーン」というのをやりました。「麦からビール、さとうきびから味の素」というコピーの広告を盛んに打ちました。いわんとするところは、原料は自然なものを使用しているということです。
この広告を見て「そうだったのか」という人は相当いらしたと思います。遡れば、創業間もない頃の「原料ヘビ説」に始まり、「味の素」の原料についての誤解はそのときどきにありました。
「味の素」は、創業時から長年、小麦や脱脂大豆のタンパク質を抽出して作っていました。その後、昭和31(1956)年に、協和醗酵工業株式会社(現協和発酵キリン株式会社)が発酵法でグルタミン酸を製造する方法を開発して、同社と味の素社はほとんど同時に発酵法に切り替えたのです。現在では、グルタミン酸ソーダの製造は世界中で発酵法に切り替わっています。その原料がサトウキビです。今はそういう風に作っているということを伝えたわけです。
「うま味」と「味の素」ブランドの普及・浸透
1970年代に入る前までは、「化学」という言葉は先進性、合理性、あるいは人類の知恵の勝利を感じさせるイメージのよい言葉だった。しかし、公害問題などに関心が集まるなか、「化学」の言葉が持つ印象は悪くなっていった。一方、日本で発見され研究が進んだ「うま味」への関心を高め、その味を提供する調味料としての名称は「化学調味料」ではなく「うま味調味料」であるべきと考えられるようになってきた。
「化学調味料」から「うま味調味料」へ
私が社長になってからやったことの一つが、「化学調味料」という言葉を「うま味調味料」に変えるということでした。
先ほど化学調味料工業協会という名前が出ましたが、この前身は、グルタミン酸ソーダ工業協会というものです。これは終戦間もない昭和23(1948)年に出来ました。
その後、鰹節のうま味であるイノシン酸、またシイタケのうま味であるグアニル酸を用いた調味料も製造されるようになりました。これらは核酸系調味料といって、グルタミン酸ソーダの名を冠した団体では合流するのに具合が悪い。そこで、昭和42(1967)年に日本化学調味料工業協会という名称に変更しました。
このとき、化学調味料という言葉が一般に使われるようになっていたわけですが、それはどうしてかと言うと、NHKが放送で使い始めたからです。NHKは調理の説明などの際に、戦前には「『味の素』を使って」と言っていたのですが、これは固有名詞で登録商標です。戦後、特定の企業の商品名を使うのはよろしくないということになって、そこでNHKが編み出した言葉が「化学調味料」という言葉だったのです。
当時は「化学」という言葉は非常にいい言葉でした。先進的でイメージがよかった。だから、味の素社はじめ各社も「化学調味料」という言葉を使うようになったのです。法律の条文でも、辞書でも、教科書でも、「化学調味料」という言葉が使われていました。
ところが、昭和50年代(1975年~)に入って、社会の風潮から言って、「化学」という言葉があまりよい印象を得られなくなってきました。「天然」ということが重んじられるようになってきて、「化学」というのはその反対のようなイメージになってきました。
一方、食品等の名称にはさまざまなものがありますが、化学調味料というのは少し変わった言葉です。グルタミン酸ソーダ工業協会の「グルタミン酸ソーダ」は化学用語です。ところが、次の化学調味料工業協会の「化学調味料」というのは、製造プロセスを使った名称で、何であるかを表したものではありません。それで、「化学で作った」という名称はおかしいじゃないかという意味も含めて、この名称を「うま味調味料」に変えようということになったわけです。
そこで、まず日本化学調味料工業協会は、当時私が会長を務めていたのですが、この国際シンポジウムでの決定に先だつ昭和60(1985)年2月に、日本うま味調味料協会という名称に変更しました。
うま味 umami の学術用語としての確定
ところで、「うま味」という言葉は、池田菊苗博士がグルタミン酸ソーダを発見した折に使った名前です。しかし、池田博士の発見までは、化学では4つの原味(甘味、酸味、苦味、鹹味)しか知られていませんでした。他に、料理の世界では渋味とか辛味とかの概念もあるわけですが、ヒトが感じる味覚はこの4つの基本味であるというのが、学界で認められていた説だったのです。
ところが、池田博士が発見した味は、この4つの基本味のどれにも合わない。ということは、これはまた別な基本味ではないかと池田博士が考えて、これを「うま味」と名付けて、味覚は五原味であるとしたわけです。このとき、うま味成分として池田博士が発見したものはグルタミン酸塩だということはすでにお話ししたとおりですが、後に、イノシン酸、グアニル酸もうま味であるとわかりました。
しかし、池田博士の発見の後も、味覚は四原味であるという説が通説というままでした。そこで、すでに何十年も前の日本の化学者が発見したことが、現代でも科学的に間違いない事実であるということを、世界的に認めてもらおうということになりました。まず日本の科学者に集まってもらい、さらに世界の科学者に集まってもらい、会議をやって検証してもらったのです。
その結果、昭和60(1985)年10月にハワイで開催した国際シンポジウムの場で、うま味というものは基本味であり、基本味は従来の説である四原味ではなく五原味であるということが、世界的に認められました。
このとき、ではこの新しく基本味に加わった味を、国際的な学術用語としてどう名付けるかということも議題に上がりました。議論のなかでは、「delicious」とか「good」とかいろいろな案が出たようですが、どうもしっくりこない。結局、これは池田博士が使った名前をそのまま使うしかないということになり、「umami」という表記が正式な学術用語となったのです。
次に、学術の世界で決まったこのことを、今度は社会にも普及させることにしました。そのためには、法律の条文でも、辞書・事典でも、教科書でも、この言葉を使い、説明してもらわなければなりません。これはなかなかたいへんなことでした。思い出すのは、とくに教科書について、文部省(当時)に理解してもらうのに苦労したものです。
また、日本だけでなく、世界中にも広めなくてはいけない。しかし、そうした苦労の甲斐あって、今ではほとんどの国・地域で「うま味」「umami」が正式に使われるようになったと言っていいと思います。
しかし、「化学調味料」という古い言葉が完全になくなったかというと、そうでもありません。というのは、「この商品は化学調味料を使っていません」と書いている商品が、日本にはまだ若干ある。しかし、こうしたケース以外では、「化学調味料」という言葉は使われなくなり、学界で認められた五原味の一つ「うま味」「umami」に基づく「うま味調味料」が今日の正しい名称として普及していると思います。
「味の素」「Ajinomoto」ブランドの普及
私たちは、「うま味」「umami」を世界に普及させる活動を展開する一方、商品名の「味の素」「Ajinomoto」の浸透にも努力しました。これも、今では世界で通用する名称となっていると思います。
日本発の商品を海外に出すに当たっては、英語や現地になじみのある言葉を使った名称に直してしまうケースは多いと思いますが、私たちはあくまでも「味の素」「Ajinomoto」にこだわりました。
これは表記だけでなく発音の普及も徹底しました。たとえばスペイン語圏では、「ji」は「ヒ」と読みますから、ローマ字で「Ajinomoto」と書いた場合、通常は「アヒノモト」と読まれてしまいます。しかし、これに限っては「ジ」と読んでくださいという広告活動を盛んにやったのです。それで、スペイン語圏でも、「アジノモト」という発音が浸透しています。
創業期から積極的だった海外展開
味の素社の世界展開は戦後に始まったものではない。それは創業間もない頃から始まり、戦前すでにアジアだけでなく、アメリカにも進出していた。
未知の国へ未知の味を伝える
さて、関東大震災の頃にまだ売れる商品でなかったと言いましたが、実は、「味の素」は発売して15年間、ずっと赤字だったのです。
それでも、「味の素」は早くから海外展開を熱心に進めました。発売してまだ3年、明治の終わりから大正の初めの頃のことですが、二代目鈴木三郎助さんは長男の鈴木三郎さん(後に三代目鈴木三郎助)に、朝鮮、台湾に見に行って来いと言って送り出したのです。まだ商業学校を出たばかりの18歳、日本の国でもあちこち旅行をしたことがない息子さんに、言葉もわからない海外に売りに行かせたんです。
また、大正6(1917)年にはニューヨークに事務所を開設します。当時、道面豊信さん、後に昭和23(1948)年から17年間味の素社の社長を務めた方ですが、この人がアメリカにいました。広島県立広島商業学校を出てアメリカの大学で勉強した後、ニューヨークで仕事をしていたところをスカウトして、ニューヨーク支店長にしたんです。
味の素社には、そうした進取の気象というものがありました。全く新しい商品でよくわからない、誰も名前を知らなかった「味の素」を、早くから、中国、アメリカ、そしてアジア各国に積極的に売りに出ていたのです。

私が入社した戦後間もない頃は、中国大陸から帰って来たという人たちがたくさんいました。その人たちがよく言っていたのは、中国でも「味の素」の看板はよく見かけたそうです。「美人マーク」(美人印)と呼んでいましたが、あの「味の素」のホウロウ看板と、「仁丹」(森下仁丹)の大礼服マークのホウロウ看板、この2つだけは相当山奥に行ってもあったということです。
中国には工場も4つありました。それらは終戦のときにすべて没収されましたが、今でもそれら工場の一部は稼働していると聞きます。
私が営業にいた頃は、再び海外展開を盛んにした時期となります。私の同僚、とくに課長クラスはどんどん海外勤務に出されたものです。誰それはブラジルへ行ったとか、ペルーへ行ったとか、ヨーロッパへ行ったとか、同僚たちの活躍を聞いて驚いたものです。
海外での生産は、戦後はタイの工場がいちばん最初です。昭和35(1960)年にタイアジノモトという会社を作って、工場の竣工はその2年後でした。それを皮切りに、世界各国に生産拠点を作っていきました。
歌田勝弘(うただ・かつひろ)
1925年生まれ。1947年東京帝国大学法学部政治学科卒業。同年味の素株式会社入社。1971年取締役本店業務部長、1973年常務取締役、1975年専務取締役、1979年取締役副社長、1981年同社代表取締役社長就任。1989年名誉会長。現在は特別顧問。1990~1995年経団連副会長。1995~1997年同評議委員会副議長、現在顧問。1999年日本バイオ産業人会議世話人代表を務め、日本のバイオテクノロジー振興に尽力。著書に「バイオ産業革命――21世紀、生活と社会が激変する」(2001年、学生社)。
(取材協力:NPO法人くらしとバイオプラザ21)








