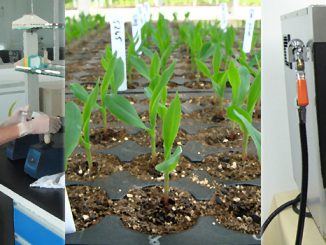【味の素特別顧問歌田勝弘さんへのインタビュー】味の素株式会社(以下、味の素社)第7代社長(1981~1989年)を務めた歌田勝弘氏に味の素社の歩みを聞き、永続するブランドと企業活動の秘訣を探った。
第1回は、味の素社が創業期から相次いで見舞われた風評・風説にいかに対応してきたかを聞いた。
インタビューでは、編集部からの簡単な質問に対して、歌田氏は詳細な内容を一息に話されたため、聞き書きの形で記した(カコミ部分は齋藤)。
日本で発見され日本で工業化された“味”
最初に、歌田氏の入社当時のことと、それまでの味の素社の歩みを聞いた。それによれば、「味の素」は明治のスタート時点から、特許や商標といった権利、公的機関による安全確認、そして親しみのある商品名を選ぶなど、ゆるぎないブランド作りに必要な要点を押さえていたことがわかる。そして、戦時下にそのブランドを封印された後、戦後に再度ブランドを作っていく再出発の時期に、歌田氏は入社した。
戦後「味の素」ブランドの再出発を共に歩む
私は昭和22(1947)年に味の素社に入社しました。私の社歴から言うと、うま味調味料「味の素」を中心とした営業、マーケティングに携わった期間が長いのですが、最初に配属されたのは、横浜の食用油の工場です。
実はあの頃、私は横浜に油の工場があるのも知らなかったし、味の素社が油を作っていることも知らなかった。でも味の素社は戦前から製油を手がけていたんです。それまでは子会社の宝製油(1935年吸収)でやっていた。満州にも工場がありました。
それで、私が入社したときにはブランドのない配給品の食用油を作っていました。戦時中に多くの食品が統制品となって、戦争が終わっても、どこのメーカーもブランドのない製品を作っていました。
それが、昭和25(1950)年になって、どうも統制解除になりそうだと伝わってきました。そうなると自分たちで売ることになります。それで、私は食用油の営業に配属されました。「味の素」の販売の部署に移ったのはその2年後ぐらい、昭和27(1952)年のことです。これは後に営業一課となる部署なのですが、当時「営業」とは言いませんでした。
草創期に意識された権利・安全・親しみ
「味の素」の歴史を簡単に紹介しておきましょう。
明治41(1908)年に、東京帝国大学教授の池田菊苗博士が、昆布のうま味の成分がグルタミン酸塩であることを発見しました。博士は、コンブのうま味は甘味、酸味、苦味、鹹味(塩味)の四原味とは違う、これは何だろうということから研究を始めたと伝えられています。
そしてグルタミン酸ソーダ(グルタミン酸ナトリウム)を主成分とする調味料の製造方法を発明して、その年の7月には特許を取得しています。
池田博士はこの特許取得と同時に、鈴木製薬所という会社の二代目鈴木三郎助に事業化の相談をしました。
この鈴木製薬所が、今日の味の素社という企業の母体で、その頃は神奈川・葉山にありました。二代目三郎助は東京で実業家として活躍していましたが、葉山の実家のお母さんがカジメという海藻を焼いてヨード製造の原料となるヨード灰を作る仕事を始めて、これが軌道に乗って設立した会社です。
同年9月に、池田博士と二代目三郎助は、この調味料の特許の権利を共有しました。ここで私が今も感心するのは、二代目三郎助は、すぐに内務省東京衛生試験所というところへ安全性の試験を依頼しているのです。そして10月13日付けで「食べ物の調味料に供すれども衛生上無害なり」という評価(衛生上無害証明)をもらっているのです。
この調味料の商品名については、池田博士は「味精」(みせい)という名前を考えました。しかし、二代目三郎助は、どうもそれじゃ売れないだろうと思った。それで考えて命名したのが「味の素」です。
これも私は感心するのですが、早くもその年の11月には「味の素」の美人印を商標登録しています。商品の安全性とブランドが大切だと考えていたことがわかります。その時代に、よくやったものだと思います。
鈴木製薬所でグルタミン酸ソーダ製造の工業化が成功し、逗子工場での生産がスタートしたのが12月で、翌明治42(1909)年に発売しました。世界に全くなかった商品の誕生です。
これが世界的な商品に成長していくわけですが、とは言え、発売からしばらくは販売するのにたいへんな苦労があったのです。
風評という試練は大正期から
「味の素」は広く普及し事業や生活になくてはならない商品になった一方、しばしば風説が立てられ、風評の影響を受けてきた。その最初のものは、発明・発売から数年という早い段階からあった。この風説はメディアも執拗に宣伝し、人々の思い込みにも根強いものがあり、払拭には苦労を要した。
風説「原料ヘビ説」に悩まされる
味の素社は風評に何べんも巻き込まれた歴史があります。その最初のものが、「原料ヘビ説」というものです。三代目鈴木三郎助さんや先輩たちから聞いていたことから、その顛末をお話ししましょう。
「味の素」がそろそろ売れ出した大正の初め頃、西暦では1915~1916年頃のことですが、どうしたわけか「『味の素』の原料はヘビだ」という風説が立つようになりました。
そもそもなぜそんな説が出て来たのか、そこはわからないのです。一説によると、当時の「味の素」の原料は小麦のタンパク質だったのですが、小麦粉を溶かしたものを樽に入れて大八車で運んで来て、それを工場の前でひっくり返してしまって、そのどろどろしたものがこぼれてニョロニョロニョロっと広がったのがヘビに見えたのではないかとかと言いますが、よくわからない。

最初は巷の噂でした。昔の盛り場や縁日には、ヘビを見せてお客を集めて薬を売る人が現れたものですが、その人たちが「今売れ出している『味の素』というのは実はこれだ」みたいなことを言い出したようです。

ところが、そのデマが雑誌に掲載されるようになります。たとえば、宮武外骨(1867―1955/著述家、編集者)が出していた「スコブル」という雑誌の大正7(1918)年10月1日号に「面白い懸賞」という記事があって、これはヘビのイラストを示しておいて「『味の素』の原料は何か」と書いたものでした。また、同じく雑誌「赤」の大正8(1919)年10月1日号には、「文明的新調味料味の素」と書いた吸い物椀から数匹のヘビがはい出ているイラストが掲載されました。
こういうことが続きまして、実際には小麦粉が原料であるのに「原料ヘビ説」を信じる人が増えてきてしまった。これは放っておけないということで、二代目鈴木三郎助は本当のことを伝える広告を始めました。
まず盛んにやったのはチンドン屋による街頭宣伝です。そして、大正11(1922)年には新聞に「誓って天下に声明す/味の素は断じてヘビを原料とせず」という社長名による声明文の広告(下欄に全文)を出しました。声明文の広告というのは、あまりなかったものだと思いますが、そこまでやったのです。
また、大正8(1919)年には、「味の素」発売10周年記念として川崎の製造工場の見学会を行って、小麦粉を原料にタンパク質を抽出してグルタミン酸ソーダを作っているんだというところをお見せしたんです。ところが、帰りの送迎バスの中、見学者が「今日はいいところをよく見せてくれたけど、さすがにヘビは見せなかったな」と言っていた。それで、ご案内した社員は実にがっかりしたという記録が残っています。
それぐらい原料ヘビ説というのは根強く伝わっていたわけです。それを打ち消すのにたいへん苦労したと、諸先輩からよく聞かされたものです。
「味の素」原料ヘビ説に対する社長声明の広告の全文
誓て天下に聲明す
味の素は斷じて蛇を原料とせず
味の素は蛇より製造するものなりとの妄語坊間の一部に流布せられつゝありと聞くや久し、然れども弊社は多く之を意に介せず敢えて進んで其妄を辯ぜんとも試みざりき、蓋し此妄語たるや味の素の卓越せる風味が偶々蛇は極めて美味なりとの古來よりの傳説を連想せしめ延て一種機微なる心理作用の下に想像せられたる空言にして畢竟味の素が如何に美味なる調味料なるかを裏書する以外大方各位を感ずべく餘りに附會に過ぎたりと深く窃に信じたればなり、焉んぞ圖らん此妄語は故らに味の素を中傷せんとする禍心より出でたるものにして筆舌相傳へ都鄙頗る宣傳せられ、今や疑心が將に暗鬼たらんとする虞れあるに至らんとは。
味の素は斷じて蛇を原料とするものにあらず、雪白なる小麥粉中より其蛋白質を抽出し進歩せる深奧なる學理に據り複雜なる操作を處して學名グルタミン酸曹達を製造し更に之を結晶せしめて粉末となしたるものに外ならず。
弊社は寡聞にして未だ蛇の如き動物よりグルタミン酸曹達を製出すべき學理的可能性すら之を知らず況んや、弊社自らが實地に之を試みて味の素を製造しつゝありと言ふに於てをや、誣妄も亦甚しく弊社の遺憾淘に之に過ぐるものあらざるなり。
弊社が江湖に薦めつゝある味の素は斷じて蛇を原料とするものにあらざる事を弊社は其名譽を賭し全責任を負て茲に謹んで江湖に聲明す羃くは、弊社誠意のある處を諒とせられ無稽の妄語に累せられ給はざらん事を。
東京市京橋区南傳馬町一丁目十二番地
味の素本舗 株式会社鈴木商店
取締役社長 鈴木三郎助
(東京朝日新聞1922年5月13日掲載/「味の素グループの百年――新価値創造と開拓者精神」〈2009年、味の素株式会社〉の図版より編集部採字。旧字の一部を新字で代用しています)
「原料ヘビ説」の収束
それでも、昭和に入ると、原料ヘビ説もだんだん消えてきました。それは、広告などの活動の効果もありますが、ほかにも事実の理解が広がるきっかけになったと考えられるものがあります。
発売から十余年の大正12(1923)年、まだまだよく売れる商品にはなっていなかった頃ですが、関東大震災で川崎工場が全壊しました。それでばたっと品物が出なくなったら、「あの『味の素』どこ行った、どこ行った」という声が聞かれるようになってきた。また、工場では原料の小麦粉を放出して、困っている人たちに奉仕したのです。
すると、「味の素社はいいことをしている」と評判になって、同時に「そう言えば、『味の素』の原料は小麦なんだな」という認識が深まった、そういう説もあります。
さらに、昭和2(1927)年に宮内省御用達の認可をいただいた。そのことも原料ヘビ説が下火になる要因になったのではないかと聞いています。
営業上有利な話でも信用できないものは利用しない
風説には悪評ばかりではなく、ときに販売促進に有利に働くように思えるものも現れる。「味の素」の場合のそれは、「頭がよくなる薬」というものだった。しかし、味の素社はこれを受け容れなかった。
「ブレイン・メディシン説」を完全無視
さて、これからお話することは、味の素社の社史にも書かないことにしている事柄です。味の素社としては、あまり話題にしたくない。しかし、味の素社が悪いことをしたので秘密にしたいというようなことではないのでお話します。
これは私も販売の現場にいたのでよく知っていることです。昭和20年代(1945年~)の半ば頃、アメリカの有名な雑誌「リーダーズ・ダイジェスト」(Reader’s Digest)に、ある記事が載りました。それは、「グルタミン酸ソーダはブレイン・メディシンである」つまり、「味の素」は頭がよくなる薬だという記事が載ったのです。
それで、その頃進駐軍の兵士がたくさんいたわけですが、彼らが「味の素」の大きな缶を買っていくのです。自分の子供の頭をよくするのに効く薬だということで、アメリカに帰るときのお土産にする。それをオブラートに包んで子供に飲ませるというのが流行り出したのです。
「リーダーズ・ダイジェスト」は戦後日本版も発行されていましたから、この記事は国内でも話題になりました。国内では、さらにいろいろな雑誌も同様の話題を載せました。とくに、慶応大学の医学博士で、林髞(はやし・たかし/1897―1969)さんという方、またの名を推理小説家の木々高太郎という人ですが、この先生がさかんにグルタミン酸ソーダはブレイン・メディシンだという話を広めて、さらにまたいろいろな人がそれを話題にしてという形で、話がどんどん広がっていきました。
あの頃、私は営業の第一線にいたのですが、「リーダーズ・ダイジェスト」の記事を読んだときの正直な気持ちを言えば、「これはうまい話が来たな」と思ったんです。ところが、トップからは絶対にその話を営業に使ってはいかんという命令が出たのです。ですから、会社としてはこれを宣伝には一切使いませんでした。
ブレイン・メディシン説は、グルタミン酸ソーダはアミノ酸の一種だから、これに頭の働きをよくする効果があるだろうといった話です。それをある科学者が言い出したことには違いありませんが、実験を重ねるなど深い追究はしていない話ですから、この説をうっかり宣伝に使うのはまずいという判断だったのでしょう。
これはやはり卓見であったと思います。
安全への関心が高まる時代に受けた最大の逆風
「味の素」だけでなく、世界のうま味調味料業界に深刻な打撃を与えたのが、オルニー(John Olney)による恣意的な実験結果の論文発表であった。味の素社はじめ世界の同業各社は科学的な検証を求める活動を展開したが、公的機関による安全宣言が出るまでには10年の歳月を要した。
オルニーのグルタミン酸ソーダ有害説の衝撃
また、昭和44(1969)年5月には、思いもよらない話が突然出てきました。アメリカの、ワシントン大学のオルニー博士が、グルタミン酸ソーダに関する論文を科学雑誌「Science」に発表して、これが1日で世界中に伝わった――マウスにグルタミン酸ソーダを投与した結果、脳の視床下部に損傷があったという研究発表でした。
私が大阪支店長を務めていたときのことです。これにはびっくりしました。
ちょうど、チクロに発がん性や催奇形性の疑いがあるということで日本でも使えなくなり、そのことが話題になった年です。その頃はラルフ・ネーダー(Ralph Nader)という消費者運動家が安全性の問題を取り上げて、消費者運動をやっていた。日本でも水俣病などをきっかけに公害や食の安全への関心が高まっている、そういう時代でもありました。
ですから、オルニー博士の論文の話題も、本当に一晩でわーっと広まった印象があります。私たちもどういうことだ、どういうことだと大騒ぎになりました。
そこで、まず科学者に来てもらって説明を受けました。オルニー博士の実験とは、生まれたばかりのマウスに、グルタミン酸ソーダを皮下注射するという実験です。食品として食べるのに比べれば大量に、しかも経口ではなく皮下注射でやっているわけです。そういうことをした結果、視床下部に損傷を来した、その実験結果自体は間違いとは言えない。しかしこれは、使ったものがグルタミン酸ソーダでなくても異常が起こる可能性を感じさせる実験です。そもそも食品添加物であるグルタミン酸ソーダを、人間に対してそのような使い方をすることはなく、普通に使っている分には問題ないということです。
そこで、大阪支店長の私も、スーパーマーケットやデパートへうかがって、朝礼に出させてもらって、店員さんたちに直接、今こういうニュースが流れているけれども、実はこういうことで問題はないのだと説明して回りました。何しろ、店のほうでは全部引っ込めるという話になっているのです。そういうことのないようにしてくれと頼んで歩いたのです。
また、その頃「チャイニーズ・レストラン・シンドローム」(Chinese Restaurant Syndrome)というのもアメリカで騒がれました。中華料理を食べた人が、頭痛がしたり、顔が赤くなったり、体がしびれたりとか、そういうことがあったという話で、その原因はグルタミン酸ソーダであるという説が、これがまたメディアで紹介されました。
これらに対して、私たち味の素社としてももちろんのこと、その頃には日本化学調味料工業協会(現・日本うま味調味料協会)という団体を組織していましたが、この団体としても、安全性の確認と、誤った情報への対処について、さまざまな活動をしました。そのなかで、イギリスのハンチントン研究所(Huntingdon Life Sciences)や日本の国立予防衛生研究所(現・国立感染症研究所)など、あちこちの研究機関に試験をしてもらい、FDA(アメリカ食品医薬品局)も見解を出してくれました。また、同業の世界中のメーカーが集まって国際会議も開催した。
結局、FDAが「グルタミン酸ソーダは現行使用レベルで食品添加物として安全である」とする安全宣言を発表したのが昭和55(1980)年。オルニー博士の論文発表から10年以上かかったのです。
歌田勝弘(うただ・かつひろ)
1925年生まれ。1947年東京帝国大学法学部政治学科卒業。同年味の素株式会社入社。1971年取締役本店業務部長、1973年常務取締役、1975年専務取締役、1979年取締役副社長、1981年同社代表取締役社長就任。1989年名誉会長。現在は特別顧問。1990~1995年経団連副会長。1995~1997年同評議委員会副議長、現在顧問。1999年日本バイオ産業人会議世話人代表を務め、日本のバイオテクノロジー振興に尽力。著書に「バイオ産業革命――21世紀、生活と社会が激変する」(2001年、学生社)。
(取材協力:NPO法人くらしとバイオプラザ21)