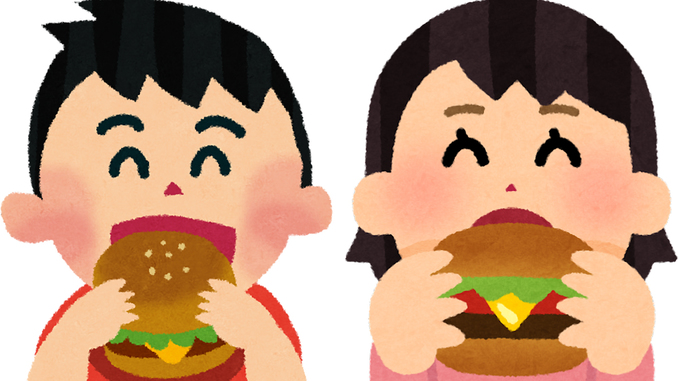
米国マクドナルド社は5月にロシア事業を地元のフランチャイジーに売却して撤退し、その地元企業は6月12日に「フクースナ・イ・トーチカ」という名のハンバーガー店として15店を再スタートさせました。
「フクースナ・イ・トーチカ」(Вкусно – и точка)の「フクースナ」は「おいしい」の意味とのこと。「トーチカ」というのはマシンガンの銃座をコンクリートでおおった陣地であるトーチカと同じ語なので、さすが戦争好きな国では店の名も物騒なものだとも思いましたが、語そのものの意味は「点」ということです。戦場では点状に配置した陣地ということでしょうが、この店名の場合は「ドット」、日本の文章で使う句点「。」のこと。つまり、「フクースナ・イ・トーチカ」というのは「おいしい、まる」「おいしい、以上」ということになります。ニュースサイトでは「おいしい。それだけ」(時事)、「おいしい。ただそれだけ」(日経ビジネス)という訳が使われています。
この「おいしい。それだけ」なる店名は、飲食店/レストランの価値を考える上でたいへん示唆に富むものと感じます。
私はロシアの現地を知らないので、この店の実際の商品のことやお客の感想などはニュース記事や動画から想像するしかありません。ただ、ロシア国内にあった「マクドナルド」に対するサプライヤーは相当に現地化が進んでいたようなので、「フクースナ・イ・トーチカ」が「マクドナルド」の同等品(ジェネリック)を提供すること自体は難しいことではないでしょう。ですから、「おいしい」と評価される可能性は十分あるでしょう。
問題は、「それだけ」でいいのか、というところです。
「FUN PLACE TO GO」
日本マクドナルドでは、同社を創業した藤田田(ふじた・でん)の時代から「FUN PLACE TO GO」というキーワードを使っています。「行って楽しいところ」といった意味です。米国生まれのマクドナルド・ビジネスに「笑顔」を持ち込んだのは藤田田で、このキーワード自体は日本地域独自のものと思われますが、米国マクドナルド社も、創業の早い段階から、商品=食べ物以外の特徴、魅力を持つように展開してきました。
「マクドナルド」は1940年代後半に、マクドナルド兄弟が米国カリフォルニア州サンバーナーディーノでスタートし、イリノイ州シカゴを拠点としていた起業家レイ・クロックが1955年に兄弟からフランチャイズ展開権を買い取って本格的なチェーン展開に乗り出したものです。
その、今日に至る「マクドナルド」の基本的なシステムを作ったマクドナルド兄弟は、レイ・クロックと契約する以前に、すでに他人の店10店とライセンス契約を結び、フリラック・アイスクリームという会社ともフランチャイズ契約を結んでいました。また、独立開業希望者に対して厨房を公開してわずかな費用でノウハウを伝えることもしていたと言われています。
ということは、レイ・クロックは、彼がチェーン展開に着手する時点で、同じノウハウで同じものを売るライバルがすでにいて、さらに競合店が増えることは容易に想像できたのです。やがては兄弟が開発したスピード調理システムで高品質な商品を安定して提供し続けることは、世界中で誰もが普通に行う一般的なことになっていくということも、彼は想像したでしょう。
そこで、レイ・クロックがマクドナルド・ビジネスの初期に考えたことは「おいしい、それだけではだめだ」ということだったのです。
レイ・クロックが取った営業上の戦略の根幹はファミリー向けのビジネスとし、とくに子供ウケすることでした。そのなかで道化師を雇い、やがてそれはRonald McDonald(日本ではドナルド・マクドナルド)というチェーン独自のキャラクターとして商標登録され、これを中心としたその他のキャラクターも増やし、一つの世界観を打ち出すに至りました。また、子供を呼び込むための仕掛けはほかにも、遊具の設置、誕生日パーティや店舗見学ツアーの企画など多くのものがあります。
「子供だましか」と思うかもしれません。しかし、子供向けにプロモーションを行うということは、子供だけを顧客とするビジネスを意味しません。最初子供として来店した人は、成長するに従ってやがて親とは別に、自分のお金で来店するようになり、今度は家族ではなく友達や恋人と来店し、いずれは子供を連れて来店する親になっていく。そのように安定した経営が可能な将来を企図したものでした。
ここで消費者側に視点を移してみましょう。子供の頃から長く来店している顧客にとって、その店はもはや、おいしいものを食べるためだけの場所ではありません。そこには、幼い頃からの多くの思い出があり、これからも行けばまた何か新しい思い出が出来る予感をさせる場所になっているはずです。
自宅を超える価値を考える
さて、コロナ禍を通じて、消費者の多くが外食から内食にシフトし、外食の利用もテイクアウトや宅配に重点を移しました。店舗での食事という行動が極端に少ない期間でした。この期間、消費者は飲食店の店舗で過ごす時間というものがほとんどないので、飲食店が提供するものに期待する価値の重心は「おいしさ」に傾いたと言えるでしょう。
(ただし、飲食店がテイクアウトや宅配で提供した「おいしさ」は、持ち帰って食べておいしいものを提供することについては一日の長があるスーパーやコンビニの惣菜や弁当等よりも優れていたのか、あるいは消費者が自分で料理した内食より優れていたのか、そこはしっかり検証しておく必要があるでしょう)
そして現在。3月以降、より顕著な数字が現れた時期としては5月以降、外食の業績は好転しています。そのなかで、意識しなければいけないことの一つは、店舗の“FUN PLACE TO GO”(楽しいから行く場所)としての価値を、以前よりも一層高める必要があるということです。というのは、消費者の多くが、自宅の居心地のよさに改めて気づいたはずだからです。家というのは、その人が気に入ったもので満たされているでしょう。好きな人がいたり、あるいは誰にも邪魔されない一人の空間であったりするでしょう。店でありがちな、注文が通っているかどうかを心配するというようなことも、見知らぬお客から不愉快な目に遭わされることもありません。
それでもレストランは、そのようなものにも優る、あえて行くべき価値がある。そのように感じさせるなにかを、レストランはもう一度用意し直さなければならない岐路に立たされているでしょう。
ロシアで「おいしい。それだけ」と言っている店でさえ、うれしそうに人が集まっている様子をビデオで見ながら、そこにあるものは実はおいしさだけではない何なのだろうかというあたりを、しっかり考えていきたいと思います。
※このコラムはメールマガジンで公開したものです。




