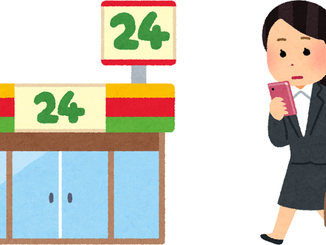「あれを食べないと夜も日も明けない」というような好物というものは持たないながら、11月になると新そばをいただきたくなります。それは山形の取材でいわゆる田舎そばの味を知ってからのことです。
そのあたりのことを以前個人ブログに書いたものを以下に再録してみます。話はそばというよりも農業の“担い手”なるものについてです。
◆
そばどころと言えば信州というイメージもあるが、山形県を一周すると、「山形こそはそばどころ」と思わされる。
10年ほど前、1週間かけてカメラマンと雑誌「そばうどん」(柴田書店)の取材で県内をかけずり回った。そばの話を聞いて、写真を撮って、撮影後のそばをごちそうになってというのを、朝一番から日が暮れるまで続ける毎日。一緒に回ったカメラマンの高瀬信夫氏は当時「こんなにそばばかり食べてられませんよ」とブーブー言っていたが、今では大のそばファンで「店を開こうか」というほどのそば打ちになってしまった。
地域や店ごとにそばの打ち方、食べ方は様々で、これぞ「山形そば」というスタイルがあるわけではないが、比較的よく出くわすのは特別に太い田舎そばだ。割り箸ほどの太さのそばを打ち、すすったりはせず、もぐもぐと食べる。すすると「もぐもぐ食べなさい」と優しく注意されるし、そばばかり食べていると「おかずも食べなさい」とまた優しく注意される。まるっきり、“ごはん”の感覚だ。
これを板のような浅い箱に盛って供し始めたのが、村山市の名店「あらきそば」。「板に持ったから」というので「板そば」と命名。この名称を他の店でも使うことが多い。
ちなみに、戦後は機械化やデスクワークが増えて人々が体力をさほど使わなくなり、そばを一度に食べ切る量が減ったため、現在はかつてより少ないポーションをメインにしている(しかし食べてみると、そばが大好きな私なども十分満腹)。その名は、「盛りが薄いから」というので「うす毛利」。で、もともとの大ポーションは「昔から出しているから」というので「むかし毛利」。
「荒木又右衛門ファンだった」というので「あらきそば」と命名した初代、たいへん魅力ある人だったようだ。
名店と言われる店は、「七兵衛そば」(大石田町)、「きよそば」(同)など他にもたくさんある。それら名店でお話を聞いていると、ある共通のストーリーが出て来る。
「このへんでは、お嫁さんは姑からそば打ちをしっかり教わる。そばを上手に打てないことは恥ずかしいことだった。そばは日常食で、農作業の後、家に帰ってそばを食べるというのが、かつてはどの家でも普通のことだった。でも、村の中で何人か上手な人がいて、だんだん『あいつのところで食うべ』と、日常的に村の人が集まるようになってきた。そうしていると、ある日保健所の人が『営業許可を取りなさい』と言いに来た。それで仕方がないから営業許可を取った。すると今度はムラの人だけじゃなく、どこで聞いたのか仙台や東京など都会のそば好きの人も、『食べさせてもらえますか?』と来るようになって、とうとう本当のお店になってしまった」
昔からみんながそばを食べていたわけだが、そばは“生活”であり、かつて山形にそば打ちという“ビジネス”はなかった。それが、いつしかおいしいそばを作る人のところに集中するようになり、プロが誕生し、事業となり、有名になり、ついに「山形こそはそばどころ」となるまでに発展したのだ。
昨今、営農が放棄されて草ぼうぼうになった田んぼを新幹線などから眺めるたび、いつもこのストーリーを思い出す。かつてコメ生産は生活であり、ビジネスではなかった。それが、いつしか上手な人のところに営農とマネジメントが集中するようになり、プロが誕生し、事業となり……。草ぼうぼうはやがて、上手な人がまた管理するようになるだろう。コメ業界は今、全国各地に続々と生まれつつあるのだ。
そして、他の作物も。
※このコラムはメールマガジンで公開したものです。