
スクリーンの餐
フードとアートをつなぐもの
2021年製作の田邊アツシ監督作品「マゴーネ 土田康彦『運命の交差点』についての研究」は、イタリア・ヴェネツィア沖のムラーノ島にアトリエを構える日本人唯一のヴェネツィアン・グラス作家、土田康彦の創作活動と来訪者との出会いを8年間にわたって記録しながら、監督自身がナレーターを務め、土田康彦論を語る異色のドキュメンタリーである。






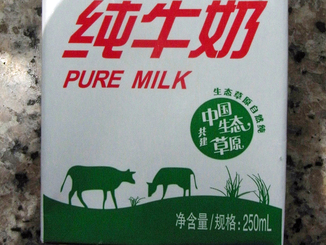

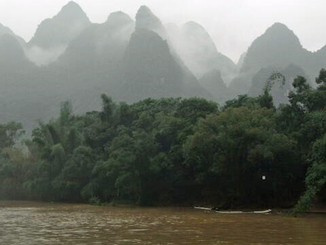
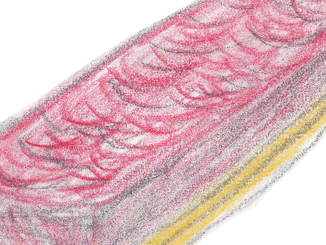




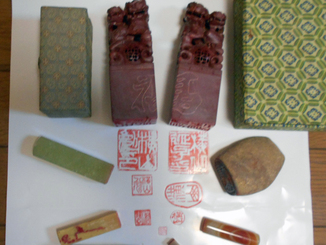
Copyright © Kosetsusha, Inc. All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.