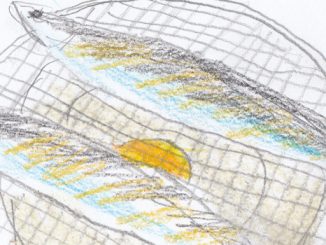鹿島茂氏のエッセーで、「メリヤスの逆説」という面白いキーワードに出会った(「ア・プロポ」:中公文庫「クロワッサンとベレー帽」所収)。メリヤスは1本の糸を編んで作る編み物のこと。また、機械編みの衣料品を指す(ちなみに、縦糸と横糸の2本の糸で作るのは織物)。ところが、今日、メリヤスは「専門の業者以外には口にしない死語になってしまっている」。鹿島氏自身、メリヤスは素材のことと思い込んでいたという。
メリヤスは、なぜ死語になってしまったのか。鹿島氏によれば、それはテクノロジーの進歩によって「生産者と消費者のあいだの距離が大きくなりすぎたため、消費者が結果、つまり『生産物』だけしか気にとめなくなり、織物か編物(メリヤス)かという『生産の過程』などはどうでもよくなったから」だ。
カレーライスのライスを除いた部分、つまり「カレー」のことを「ルー」という人が多い。しかし、ルーというのは本来は油脂(サラダ油、バター、ラードなど)に小麦粉を振り入れて炒め、水分を加えたものを言う。これにスパイスを加えて調製したものが「カレールー」となり、その製造を工業化したものがスーパーなどの店頭に並んでいる。消費者の多くは本来のルーを作ったり見たりしたことがなく(本当は、料理本を見ながらホワイトソースを作るときなどに、ルーを作っていることもあるが、それがルーだと知らずにいる)、いつの間にかカレーライスのライス以外の部分を指すときに「ルー」と言うようになってしまった。
これなどは、正確には「メリヤスの逆説」の例とは言えないが、製造技術と流通が高度化した結果、生産と消費が隔絶され、言葉の本来の意味が失われた一例と言える。
今日の消費者の多くは、最終製品だけを目にし、口にする。生産、製造がどうなっているのかは、関係者以外にはほとんど分からない。そしてその間、技術はさらに進歩し、高度化している。それが今日の流通だ。
ところが、ローテクのことはまだ案外よく知っている。ここでローテクというのは、特別な設備や材料を必要としない簡素な方法という意味で、技が幼稚だというマイナスの意味ではない。肉の焼き方、魚の煮方、野菜の刻み方など、上手下手はあっても、まだそれなりに理解している消費者は多い。むしろ、休日に相当凝った料理を作り、研鑽の程度が低い料理店よりもうまいものを作る消費者もいる。また、家庭菜園や市民農園で、相当に品質のよい野菜を作る名人芸を持つ消費者もいる。
そういう人自身、あるいはそういう人を身近に見て知っている人にとって、食品の善し悪しを判断する基準は、ローテクで使っているモノサシとなる。だから、餅を冷凍したり、細かくカットした肉を結着したりという話を突然聞かされると、「知っている作り方と違う」と感じ、違和感を抱く。表示をきちんとしているかどうかという問題とは全く異なるレベルで、拒絶反応を起こす。
逆に、麺類を店頭で打って見せたり、レジの裏のガラス張りの厨房でパン生地をこねている様子を見せたり、すしが回るレーンの内側ですしを握って見せたりと、スクラッチであることを強調する飲食店は、「そうそう。それがそば(うどん、パン、すし)だ」と人気を集める。
食品メーカーも、消費者がスクラッチに弱いと理解していて、テレビCMや印刷物では、生身の人間が手で作っている場面などを見せ、極力それがローテクで作られている印象を与えようとする。それが悪いとは言わないが、疑問もある。
ハイテクで作られているものについてローテクで作っている印象を与えることに成功するということは、法的に問題ない場合でも、隠蔽にほかならない。それは、さらに今日の食品製造の実際と消費者の知識を引き離すことに外ならない。食品における「メリヤスの逆説」化を促進し、食品に対する正しい理解を妨げ、文化を損なうことになる。
かつて英国の社会人類学者ジェフリー・ゴーラーが、「死のポルノグラフィー化」という言葉を使った。本来の死、実際には身近にある死が隠蔽され、人々は映像でしか死に触れなくなっていることを指す。人々は死のリアリティを失い、死に対して歪んだ好奇の目を向けている。それに照らせば、食品について、「生産のポルノグラフィー化」が進んでいると言えないか。
ハイテクで食品製造を行う人々は、自分たちがしていることに自信がないのだろうか。自分たちがしていることは、人々が嫌がることだと思っているのだろうか。気味の悪い、おかしなことをしていると思っているのだろうか。ローテクが“表”で、ハイテクは“裏”だとでも思っているのだろうか。
では、例えば。木でできた臼と杵でかけ声をかけながらつく餅つきが“表”で、餅つき器は“裏”だろうか。子供たちは、どちらを見るときも目をらんらんとさせて、面白そうに見ている。「クリスピー・クリーム」は、ドーナツ製造をオートメション化し、店内に設置した機械が動く様子をガラス越しに見せる「ドーナツ・シアター」を売りの一つにしている。喜んで観ているのは子供だけでなく、大人たちも面白そうに眺め、そこから出てきたドーナツをうれしそうに持ち帰っている。
見学コースを持つ食品工場では、コースの終わりにある売店で製品がよく売れる。それだけでなく、彼らは観てきたことをひとにも熱っぽくよく話す。工場の技術者が、自分たちが使う機械について、奥ゆかしくも自慢として話したときなどいちころだ。それは、シェフが自分の料理を語る場合と同様に歓迎される。見学者はその会社の製品のファンになり、何人かはその会社で働きたいとも思う。
今の、本当のことを、語り、誇ることに、何の損があるのか。
※このコラムは「FoodScience」(日経BP社)で発表され、同サイト閉鎖後に筆者の了解を得て「FoodWatchJapan」で無償公開しているものです。