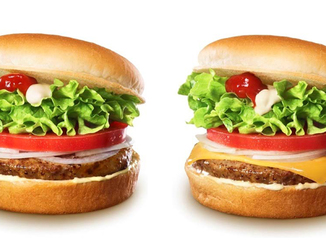長年農業高校で教鞭をとってきた栃木県の稲葉光國氏は、10年ほど前に約30年間の教諭生活に終止符を打ち、97年に民間稲作研究所(現在はNPO法人)を設立した。化学肥料や農薬を使わない稲作の体系作りと普及に専念するためで、現在は活動を全国規模に広げ、各地の生産者が稲葉氏の方法の実践と結果のフィードバックを行っている。
同研究所が薦める稲作のポイントはいくつかあるが、一例を挙げると以下のようなものがある。
(1)冬季湛水あるいは早期湛水(作付け前の水田に水を入れる)で生物相の確保、雑草の抑制。
(2)大豆作後の水稲作で雑草の発芽を抑制(1作のみ有効)。
(3)葉齢5(5枚の葉が揃った段階の苗)の成苗移植(通常の水稲作では葉齢3.5程度)でネグサレ防止、イネミズゾウムシ害の克服。
(4)栽培早期から水深を深く保つ深水管理で、雑草の発芽、伸長を抑制。
(5)最終分げつ(茎が分かれて増えること。その茎)を伸長させ、穂の1粒当たりの葉面積を小さくする「太茎・大穂」の戦略で安定多収。
同様の方法を提案している団体や生産者は他にもあり、有機農法に関心のある向きにはなじみのある手法が含まれているはずだ。同研究会は、こうしたポイントの一つひとつが具体的にどのような効果につながるのかのデータを取り、可能な限りその理由やメカニズムにまで迫り、さらに全体として一つの体系として完成させようとしている点で農家有志の期待を集め、根強い支持を受けている。
いずれも、化学肥料や農薬を使わないための工夫だが、そもそもなぜそれらの不使用を目指すのか。稲葉氏は、「有機農業は環境を守り、安全性を高めるための技術。行政などからは単に高付加価値商品を作ることと見られることが多いが、それは本意ではない」と力説する。だが、有機農法に取り組み始めたのには、もう一つの動機もあったと言う。
「化学肥料や農薬を使う水稲作はコストがかかり過ぎる。ところが、米国、オーストラリア、中国などは高収量、低コストの稲作を行っている。ウルグアイラウンドで海外産のコメが現実の脅威となった時、このまま続けていては、国産米は価格と品質で太刀打ちできないと分析した」
その危機感から、各地の農家に教えを乞いながら新しい栽培体系の研究を始めた。しかし、普及の道は決して平坦ではない。前述の手法の例で言えば、(1)については水利権がネックになるケースが多い。(2)はダイズ価格の安さから、二の足を踏む農家が出る。(3)~(5)は現在の通常の水稲作の常識との差が大きい。稲葉氏自身、この体系がモノになり始めた時、「教科書と違うことを教えねばならない矛盾を感じて農業高校を退職した」。また、実態はサラリーマンといった兼業農家には不可能なものもある。
そして何より障害となるのは、そもそも化学肥料と農薬を使わないということそのもの。というのも、多くの農家は化学肥料と農薬を使う“義務”を負っているからだ。
収穫したコメは売らなければ話にならない。では農家はどこに出荷するかと言えば、ほとんどは地元の農協だ(系統出荷)。その農協にとって、化学肥料と農薬を売ることは重要な収入源となっている。また、農協のほかに産地卸などへ出荷する手もあるが(商系出荷)、その相手は化学肥料や農薬の卸商である場合も多い。つまり、化学肥料や農薬を買わなければ、集荷もしてもらえないという構造がある。
古い常識と社会的・経済的な構造という二つの壁がある。農家がそれを乗り越えようとすれば、「なんでお前のところだけ違うことをするのだ」と文句を言われることにもなる。
それでも、稲葉氏は、さらに普及を急がねばと言う。「3月1日施行の有機JAS改正で、禁止資材に関する項目など有機認証の基準がさらに厳しくなる。これで有利になるのは、降雨が少なく、もともとオーガニックに取り組みやすい大規模圃場を擁する米国など海外の産地」だからだ。
氏の言葉から連想するものがある。GM(遺伝子組換え)作物の試験栽培や導入・普及を訴える農家たちの、「今、手をこまぬいていては、海外産地に負ける」とする声だ。海外で既に普及し、実績を上げている技術の導入の遅れが、国内農業の敗北を招く。ところが、誤った常識と社会的・経済的な構造がそれを阻んでいる――稲葉氏とGM推進派と、両方からお叱りを受けそうだが、両者が心に抱く思いは同じものに見える。
黒船は来ている。犬猿の仲と言われた薩長の同盟でかつては乗り切ったが……。
※このコラムは「FoodScience」(日経BP社)で発表され、同サイト閉鎖後に筆者の了解を得て「FoodWatchJapan」で無償公開しているものです。