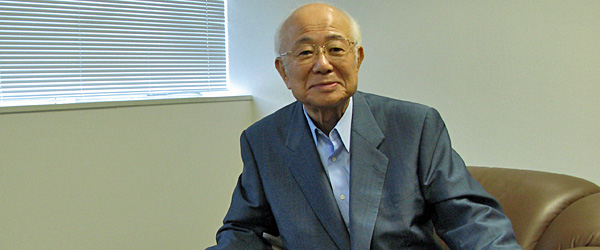
【味の素特別顧問歌田勝弘さんへのインタビュー】味の素株式会社(以下、味の素社)第7代社長(1981~1989年)を務めた歌田勝弘氏に味の素社の歩みを聞き、永続するブランドと企業活動の秘訣を探った。
第4回は、前回に続いて産業と社会の変容のなかで下した大きな決断について聞いた。また、日本のバイオテクノロジー、バイオインダストリーの振興について、味の素の歩みを振り返ることが役立つと感じさせる話題が提供された。
インタビューでは、編集部からの簡単な質問に対して、歌田氏は詳細な内容を一息に話されたため、聞き書きの形で記した(カコミ部分は齋藤)。
日本で学び世界へ応用したマーチャンダイジング
「ほんだし」の真の成功は、新発売その時点よりも、むしろ売上げが伸び悩む地域を観察し、そこに対応するバリエーションを作った段階に到来したと言える。そこで学んだことが、やがて世界へ展開されていく。
「ほんだし」で学んだ地域対応
さて、風味調味料を売り出すという公約が「ほんだし」の発売で実現し、しばらく経ってよく売れるようになってこれはよかったと思っていたのですが、どうも関東と関西では売れ行きが少し違うことに気付き始めました。東京ではどんどん、どんどん売れるのです。ところが、関西ではなにかちょっと詰まるところがある。どうしてかなと思ってさらにデータを見てみると、四国あたりの反応がとくに鈍いのです。
それで、四国に行ってスーパーマーケットに入ってみて、事情がわかりました。スーパーマーケットで「ほんだし」を置いてもらっている一角を見ると、いちばん手前にあるのは「ほんだし」ではなくて、だしじゃこがたくさん並んでいる。つまり、この地域でだしを取るのにはだしじゃこを使うわけです。鰹節も使わないわけではないけれど、何と言ってもだしじゃこを使う。それで「『ほんだし』いりこだし」というのを急いで出して対応しました。
こうして地域対応の大切さがわかったわけです。
「ほんだし」はそれから主力商品の一つになって、さらに国内だけでなく世界的な商品になっています。私も、着手したときはそこまで伸びるとは思っていませんでした。
そして、この「ほんだし」の世界展開でも、その地域に合わせるということが重要なポイントになっています。つまり、だしというものの味は、国によって地域によって違うわけです。日本でなら、鰹節やだしじゃこやとあるわけですが、世界の各地ごとにも、鶏、豚、牛など、好まれるものがいろいろと違う。
それに対して、「『ほんだし』いりこだし」を開発した流儀で、国・地域ごとに合ったものを作って出したら、それぞれ当たっているわけです。
グルタミン酸ソーダという基本味に、その地域ごとに好まれる風味を合わせて作る。これが風味調味料です。
今では、世界的に見て、家庭用商品としては、「味の素」や「ハイミー」という基本調味料よりも、風味調味料のほうが売上げとしては大きくなっています。
市場対応では最重要顧客との関係が変わることもある
味の素のマヨネーズ開発秘話。それは単に巨人に立ち向かうことだけでなく、最大の顧客を失うことを賭して挑む、自らも血を流す行為であった。
洋風化への対応で踏み込んだマヨネーズ
私はその後、昭和56(1971)年に取締役本店業務部長、昭和48(1973)年に常務取締役業務部担当となりました。その頃に出したものの一つが「クックドゥ」シリーズです。
先ほど、高度成長期の私たちの課題は、成熟化・多様化と洋風化にいかに対応するかということだったとお話ししましたが、「ほんだし」の次に、さらに調理食品まで入っていったらどうだということになったわけです。
洋風化への対応では、その前の昭和43(1968)年にマヨネーズを発売したということがありました。これは、多様化と洋風化への対応の一つですが、CPCがアメリカでマヨネーズを扱っていて、その技術を使ってマヨネーズをやりたいということになったのです。
しかし、これは簡単に決断できることではありませんでした。というのは、当時マヨネーズと言えばキユーピーが圧倒的なシェアを取っていましたが、そのキユーピーさんは、わが社のグルタミン酸ソーダをたくさん使ってくれていた大のお得意先だったのです。それなのに、味の素社でマヨネーズを作っていいのかという話です。私たち営業担当者としては非常に困った問題でした。
しかし、そこはトップの判断です。当時の社長の鈴木恭二さんが、自らキユーピーの創業者、中島董一郎社長を訪問した。そして、「自分はこういう決断をしました、今までご支持に与ったのに申し訳ありません」とお詫びに行ったわけです。
中島董一郎さんは当時ずいぶんご年配でした。私たち味の素社の営業担当者にとっても神様のように思う方で、うかがうときもご機嫌を損じないように丁寧にしなきゃいかんと申し合わせていたものです。
その中島さんが言われたことは、「わかりました。しかし本日をもって『味の素』は使いません」ということで、それで切られちゃったわけです。鈴木社長もそれは覚悟で行ったわけですが。
しかし、それで引き下がらない人がいたわけです。ある営業担当者が、その10日後ぐらいに中島さんのところへ訪ねて行って、ご用命いただきたいと言ったというのです。そうしたら中島さんが怒るかと思ったら感激してくれて、お前よく来たと、偉いやっちゃと言って、玄関まで送り出してくれたという話を聞いています。いや、もちろん使ってはもらえなかったわけですが。そういう逸話もあります。

そういうわけで、マヨネーズをやった事業部の人たちはたいへんな思いでやったわけですが、商品が出来て、今度は営業もたいへんでした。これは私が大阪支店長時代です。さて、これをどう売り出すか。なにしろ、マヨネーズと言えばキユーピー一色の時代です。特約店たる卸にとっても、キユーピーのマヨネーズは非常に大事な商品です。そこで味の素社が新しく作ったマヨネーズを扱ってもらえるかどうかが問題です。まず、断られて当然ぐらいのものでした。
それでも一生懸命通ってお願いして、「味の素社がやるならしょうがないなぁ。まあ扱ってやろう」とは言ってもらえたわけですが、たいていは二番手として扱ってくれるという話です。
そのなかで一軒だけ、「お前が言うなら、キユーピーには悪いけれど、キユーピーも売るけど、お前を担いでやる」と言ってくれたのが、国分商店の大阪支店長でした。この人は、私の東京時代から仲の良かった人で、その人がやはりそのとき大阪にいたのです。その人も味の素のマヨネーズをどう扱うかでは困るに困ったはずなのですが、そう言ってくれて、あれはうれしかった。
とは言え、売る側でそういうことがあっても、消費者にとって味の素社のマヨネーズが二番手であることは間違いありませんでした。それでも、味がキユーピーさんのものとは違うことと、宣伝にも力を入れたことで、伸びていきました。
この宣伝と営業でも、社内で盛んに言われたことは、決して競合の悪口を言ってはいかんということでした。自分のいいところだけ言えと。これも大事なことでした。
ともかく、これで味の素社は洋風化への対応の一つを進めることができたわけです。そして、キユーピーさんという大得意先を失いはしましたが、マヨネーズというもののマーケットが大きくなったことを考えると、これをやってよかったと思うのです。
バイテクにも戦略とパブリックリレーションが必要
歌田氏は味の素社のトップを務めた一方、産業界の振興にも力を注いできた。その一つがバイオテクノロジー、バイオインダストリーの推進。歌田氏は、この分野についても、戦略に基づいた行動と、社会との良好な関係づくりが大切だと説く。
オールジャパンの戦略と行動を
私が味の素社で働いてきたこととは別に、社外で取り組んだことの一つは、日本のバイオテクノロジーの振興です。
バイオインダストリー協会(JBA/Japan Bioindustry Association)という、バイオテクノロジー、バイオサイエンスの産業界の団体があります。私はその理事長を務めたことがありますが、そこでまず気づいたのは、日本ではこの分野に取り組む団体があちこちにあってばらばらだということでした。
バイオインダストリー協会は、通商産業省(当時)の所管でしたが、バイオテクノロジーについては、同省所管団体がほかに10ぐらいある上に、さらに厚生省(当時)にも、農林水産省にも、あるいは環境庁(当時)にも所管する団体があって、いろんなところに協会がありました。それぞれ、ちょっとずつ中身は違うのだけれど、それらがばらばらに一生懸命やっている。
私は、そういうばらばらな状態でやっていたってだめじゃないかと考えました。まず、ばらばらではなくオールジャパンで一丸とならなくてはいけない。その上で、戦略を立てること、そして国民とのコミュニケーションをすること、これが必要です。
そこでまず、平成11(1999)年に、日本バイオ産業人会議(JABEX)というのを作りました。まず、産業界が一致団結しようということです。
さらに、行政と政治もいっしょに取り組んでもらう必要がある。それで、まず当時の小渕恵三総理に会いに行って、政府、大臣、関係省庁がいっしょになって、長期的な国家戦略を作るべきだということを話しました。政治家でこの趣旨に賛同してくれた人が、ライフサイエンス推進議員連盟を作ってくれました。
なぜ総理大臣への談判であったのか
次にオールジャパンの戦略を立てる。私は、今度は小泉純一郎総理に会いに行きました。アメリカも、ヨーロッパも、中国も、シンガポールも、各国ともバイオテクノロジー、バイオインダストリーの長期的な国家戦略を持っているのに、日本にはなくて、いろいろな団体がそれぞればらばらでやっている。それではだめだから、総理大臣が声をかけて、みんなで一緒になって国家戦略を作るべきだと説明したのです。
そしたら、小泉総理は「よーし! わかった!」と言ってくれた。ところが、小泉さんは、自分が首相になる前からかかわっていたものは自分が座長になってやっていましたが、首相になってからスタートしたものは担当大臣のほうでやると言うのです。
私はそこで大きな声で「冗談ではありません!」と言ったのです。「各省にまたがってばらばらにやっているのが具合が悪いから、こうして総理大臣のところへお願いに来ているのであって、総理大臣が議長でなければ成り立ちませんよ」と。
すると小泉さんという人はまた、「よーし! わかったー!」と。オレがやると言ってくれたのです。それから毎月会議を持ってくれまして、ようやく平成14(2002)年12月に「バイオテクノロジー戦略大綱」が出来たわけです。
また、もう一つ、国民とのコミュニケーションについては、パブリックリレーション(PR)の組織を作って、国民全体に働きかけをするべきだと各方面に話しました。とくに、日本バイオ産業人会議として、PRの組織を作るべきだと話しかけたのですが、これがなかなか進まなかった。皆、総論は賛成、しかし各論になるとそれぞれに意見があってまとまらない。
たとえば、医療関係はバイオ医療というのが相当なマーケットを抱えている。また、いちばん難しかったのは食品と農業関係です。こちらは、農林水産省と、医療も所管している厚生労働省にもまたがる。そういうことで、もたもたしているわけです。
ところが、そうしている間にも、実際に日本は遺伝子組換え食品を大量に輸入して日本人は食べているわけです。それにかかわらずコミュニケーションが十分できていない。バイオテクノロジーを利用するほうではそういう事実があるにもかかわらず、日本では生産するほうでいろいろな制約があるままです。栽培するにも、実験をするにも、他の圃場とどれだけ離さないといけないとかというのもそうですが、遂には北海道をはじめ各道府県の条例で作らせないという自治体が出てきた。
国民に理解されていないから、そうした事態を招き、各国に遅れをとっているわけです。
それで、これはNPO法人で立ち上げようということで、平成14(2002)年7月にNPO法人くらしとバイオプラザ21を作ったわけです。ここが、バイオテクノロジー関係者と国民、消費者の間に立って、一方通行ではない双方向のコミュニケーションを担っています。彼らの活動に、ぜひ注目していただき、日本のバイオテクノロジーがよい方向へ進むように協力していただきたいと思っています。
《この稿おわり》
歌田勝弘(うただ・かつひろ)
1925年生まれ。1947年東京帝国大学法学部政治学科卒業。同年味の素株式会社入社。1971年取締役本店業務部長、1973年常務取締役、1975年専務取締役、1979年取締役副社長、1981年同社代表取締役社長就任。1989年名誉会長。現在は特別顧問。1990~1995年経団連副会長。1995~1997年同評議委員会副議長、現在顧問。1999年日本バイオ産業人会議世話人代表を務め、日本のバイオテクノロジー振興に尽力。著書に「バイオ産業革命――21世紀、生活と社会が激変する」(2001年、学生社)。
(取材協力:NPO法人くらしとバイオプラザ21)








