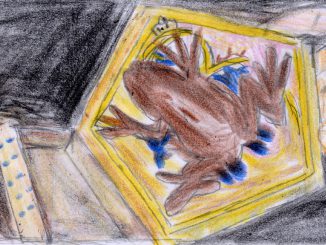東京・大久保に「ハルコㇿ」というアイヌ料理店がある。ハルコㇿとは、アイヌ語で「食べ物(穀物)・持つ」を指し、「食べ物に困らないように」という願いが込められているという。店主の宇佐照代さんは、アイヌ文化アドバイザーとして、アイヌ伝統舞踊の実演や、アイヌ伝統楽器の演奏などの活動も行っている。
今回紹介する「そして、アイヌ」は、曾祖母、祖母、母、照代さん、娘の5世代にわたる家族のライフヒストリーを紐解きながら、さまざまな立場からアイヌの文化や料理と出会った人々を通して、文化の継承とアイデンティティ、マジョリティとマイノリティ、同化政策と多様性といった問いに向き合ったドキュメンタリーである。
※注意!! 以下はネタバレを含んでいます。
レラ・チセからハルコㇿへ
照代さんは5人きょうだいの真ん中として北海道・釧路で生まれた。周囲にアイヌの人はいっぱいいたものの、自分たちがそうだとは知らされずに育ったという。照代さんは当時出自を知らされない理由がわからなかったが、今にとなってはいわれのない差別や偏見を避けるための両親の配慮だと思っている。
照代さんが10歳の頃に両親が離婚。照代さんは母のタミエさんときょうだいと共に上京した。東京には択捉島出身の祖母の西村ハツエさんがおり、照代さんはハツエさんに連れられて、歌や踊りなどのアイヌ文化を紹介するイベントに参加するように。タミエさんはハツエさんが初代会長を務めていた「レラ(風)の会」という、関東在住のアイヌ女性を中心とした親睦団体のメンバーになった。
1993年、レラの会では、関東にアイヌ料理店を作りたいという気運が盛り上がっていた。北海道には、アイヌの人々が集まれる生活館が各地にある。関東では、アイヌを名乗っていない人でも気軽に利用できる“料理店”という形がよいのではという思いがあったという。店の名前は「レラ・チセ(風の家)」に決め、全国に設立のためのカンパを募った。くしくも「国際先住民年」であったことも手伝って、半年で3,000万円が集まり、1994年5月にレラ・チセは東京・早稲田で開業した。タミエさんや照代さんも働いた店には、アイヌの人々だけでなく国内外からさまざまな民族の人々が訪れた。
2009年にレラ・チセは閉店したが、タミエさんと照代さんはレラ・チセの志を受け継ぎたいと個人で店を持つことを決め、2011年6月にハルコㇿをオープン。レラ・チセと同じようにさまざまな国や地域の人々が集まる場となり、現在に至っている。
ハルコㇿのアイヌ料理
本コラムとして気になるのはハルコㇿのメニュー。本作でもその一部が映し出されており、どれもおいしそうに見える。
ほっけの開きやザンギなど居酒屋風の料理があるなか、注目はアイヌ料理。キトピロ(行者ニンニク)の三点盛り合わせ(醤油漬け、おひたし、酢みそ)、エゾシカの炙り山わさび、チェプサンペ(鮭の心臓)のソテー、チェプ(鮭)のチャーハン、チェプのルイベ(凍った鮭の刺身)、オハウ(煮込み汁)など、他所ではなかなか味わえない料理が揃っている。

ハルコㇿに集う人々
八王子の多文化共生イベント「みんなちがってみんないい」に出店したハルコㇿ。ハスカップのかき氷が涼を感じさせる。
このイベントを通じて照代さんと20年以上交流している、朝鮮半島伝統音楽の活動グループ「誕古団」メンバーの黄秀彦さん。「アイヌ、100人のいま」プロジェクトで全国のアイヌの人々を撮り続けている写真家の宇井眞紀子さん。釧路出身の評論家でレラ・チセ設立の事務局長も務めた太田昌国さん。被差別部落出身の縄文造形作家で、縄文文化との関連性からアイヌ文化を学び、今では建物のカムイ(神)に感謝を捧げるカムイノミ祭司を務める平田篤史さん。アイヌの歴史や文化に関心を持つ美術作家の奈良美智さんなど、ハルコㇿにはアイヌと似た立場の人々や、アイヌの文化に魅せられた人々が多数集う、マイノリティの多様な文化が交わる場所となっている。
教わらなかったことと、伝えていくこと
17年ほど前、照代さんの祖母のハツエさんが倒れ、照代さんは病室に駆け付けた。ハツエさんは照代さんの手をとり「民族の誇りを持って生きていくと発表してください」と言ったという。照代さんがアイヌとして生きていくことを託された瞬間だったが、照代さんはアイヌのさまざまなことを教わっていなかったため、独学で文献を当たることになった。
あまたの国や地域においては、マジョリティがマイノリティに対して文化的同化を強いる政策が繰り返されてきた歴史がある。照代さんは独学の結果、1899年(明治32)に制定された北海道旧土人保護法(1997年に廃止)が、大多数のアイヌの人々を苦しめるきっかけになったという主張があることを知り、ハツエさんの思いを理解した。そして、自分が食文化を始めとするアイヌ文化の伝承者として生きていく決意をしたという。
そんなある日、照代さんのもとに知り合いから、照代さんの曾祖母の宇佐タマさんの生前の姿を蘇らせる“あるもの”が届く。孫、曾孫、玄孫までがアイヌとしてのタマさんの生き様を受け取るシーンは、本作のハイライトである。
照代さんの娘、ルイノさんはアイヌの歌と楽器を特訓中。閉店後のハルコㇿで、母娘マンツーマンの練習が続く。
- ハルコㇿ
- https://x.com/harukoro522
- [旧] 北海道旧土人保護法について
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_sinpou4.html
【そして、アイヌ】
- 公式サイト
- https://soshite-ainu.com/
- 作品基本データ
- 製作国:日本
- 製作年:2024年
- 公開年月日:2025年3月15日
- 上映時間:96分
- 製作会社:大宮映像製作所
- 配給:東風
- カラー/サイズ:カラー/16:9
- スタッフ
- 監督・企画:大宮浩一
- 撮影:常田高志、辻井潔、遠山慎二、田中圭、伊藤寛、伊東尚輝、北川帯寛、岩爪勝、大宮浩一
- 整音:石垣哲
- 編集:田中圭
- 編集協力:遠山慎二
- カラーコレクション:福井崇志
- キャスト
- 宇佐照代:
- 宇井眞紀子:
- 黄秀彦:
- 太田昌国:
- 平田篤史:
- 奈良美智:
- 関根美子:
- 表美智子:
- ルイノ:
- HIRO:
(参考文献:KINENOTE)